うつ病の従業員に対して求められる会社や上司の対応とは?
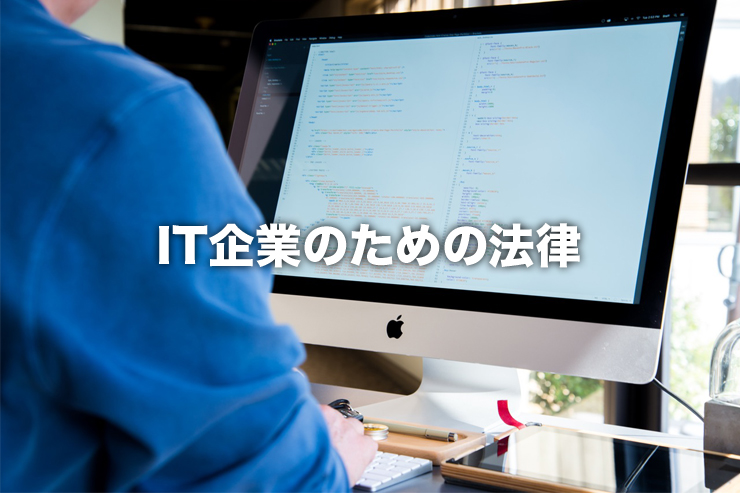
従業員がうつ病になってしまった
一昔前「うつ病」などと言ったら「根性がない」「気合いが足りない」などといったように、いわゆる精神論で片づけられていた時代もありました。
しかし、時代の移り変わりとともに、原因は諸説あるものの、性格や気分等の問題だけではなく「病気」として認識されています。
では、もし従業員に「うつ病になりました」と言われてしまった場合、またそうなる前に、会社としてはどのような対応をするべきなのでしょうか?
今回は、社員がうつ病になった時に会社がとるべき対応について、確認していきます。
労務問題は、IT企業専門社労士事務所のグローウィル社会保険労務士事務所へ
【現状把握】従業員の「いつもと違う」を見抜く!
従業員としては、いきなり、「うつ病になりました。」と診断書を突き付けられる・・・ということも少なからずあります。
やはり、体調不良で休むことが増えた、遅刻・欠勤・ミスが目立つようになった、など何かしらの症状が出てきており、それが次第に悪化してくるといったことが多いかと思います。
そのため、うつ病になる前の「いつもと違う」を見抜き、社内で対応できることで、解消できれば一番良いでしょう。
- 面談等で近況、状況を確認してあげる
- 有給休暇があれば、有給分を使って休んでもらう
- 時短勤務などの労働条件の変更
- 負担が少ない部署に異動をする
「いつもと違う」従業員の現状を把握するように心がけましょう!
【初動対応】兎にも角にも診断書を!
実際に医師にうつ病と診断されてしまった場合、まずは医師の診断書を提出してもらいましょう。
診断書を出すようにお願いするのは、いささか従業員を疑っているようでちょっと、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは、後に従業員の為にもなることです。医師の診断書は必ず取得するようにしましょう。
場合によっては、従業員の同意が必要ですが、診察に同行するのも良いでしょう。
可能な限り、受診する従業員の健康状態は把握しておきたいので、同行が出来ないようであれば、主治医との連絡についての同意を貰うようにしておくのも一つの手です。
従業員がうつ病になったとはいえ、必ずしも原因が会社とは限りません。そのため、医師の診断を確認して、次の対応を従業員と共に検討することが重要となってきます。
【休職】休職が必ずしも良い対策ではない!
病院の診断書をもとに、休職について従業員と共に考えて行くことになるでしょう。
ここで注意が必要なこととしては、あまりに過敏になりすぎて、やたらに休業を進めてしまうことです。
本人は頑張りたいと思っているにも関わらず、強引に休業をさせてしまうことは、場合によっては不当に休業をさせられたと言われる可能性もあります。
少し長めの休暇や時短勤務、部署移動等で対応できる可能性があるかも含めて従業員と決めていくのが良いでしょう。
また、就業規則等の休職要件についても注意が必要です。長らく就業規則を確認していなかった、よくよく見たら休職の要件を満たしていない、なんてこともあり得ます。
改めて、就業規則の休職要件について確認が必要です。
休職については、労使がよく話し合って決めることが不可欠です!話し合いの末、休職をすることになった場合は「休職願」などの書面を残すようにするのが良いでしょう。書面として残すことにより、後にトラブルになった際の証拠となります。
休職中の給与はどのようにしたらいいのか
基本的には会社の決め次第ですが、休職期間中は必ずしも給与を払い続ける必要はありません。しかし、従業員にとって、給与は一番の不安の種でしょう。
そのため、会社側としては、健康保険に加入していれば、「傷病手当金」等の支給手続きに協力してあげることにより、後のトラブルの種を減らすことにつながります。
休職期間満了・復職
休職期間が満了した場合、その後、どういった対応をとるかも、面談等踏まえよく話し合ってから決める必要があります。
もちろん、復職できるのが一番良いのですが、必ずしもそうとはいきません。ただ、ここまで来ると、職を辞めるか否かの話になりますので、細心の注意が必要です。
復職できる場合
症状は改善し、実際に復職が出来そうか否かについては、「無理やり復職させられた」といったトラブルになることを避けるためにも、改めて医師に診断書を発行してもらうことをおススメです。
また、可能であれば、会社指定の医師に診断書を発行してもらうことにより、セカンドオピニオンとしての効果もあり、本当に復職が可能かの判断材料にもなります。
また、復職する際も休職時と同様に「復職願」などの書面を残すようにすると良いでしょう。
復職が難しそうな場合
休職期間が満了したものの、症状の改善が見込まれず復職が難しい場合は、就業規則の規定にもよりますが「期間の満了をもって退職」と規定している会社が多い様です。
この様な規定が設けられていれば、自然退職として扱うことになるので、原則、告知がなくても退職は有効です。
ただ、ことの重要性を鑑みると、退職日や退職理由などは、文書でも通知をした方が良いかもしれません。
一方、就業規則上で休職期間満了後の退職についての規定に、特段規定がない、若しくは「解雇事由」として規定されている場合は、もちろん自然退職とはなりませんので、退職させる場合は解雇に関する手続き等をとる必要があります。
解雇となると、解雇予告や解雇予告手当の問題も当然発生しますので、特に注意が必要です。
うつ病に対する会社の対応は重要
もし、従業員がうつ病と診断されても、必ずしも会社が原因かどうかはわかりません。
しかし、傷病に対する措置を講じなかったことで、より精神を病み、最悪自殺するなどといった事態になってしまった場合、いくら会社側に「うつ病」の原因でなかったとしても、大変な事態です。
親族から訴えられたら、賠償金を支払うことになるでしょう。労働基準監督署の調査対象となれば、対応に追われるでしょう。取引先・消費者に伝わってしまったら、会社の信用は地に落ちてしまします。
会社にとって大切なもの全てが失われてしまうかもしれません。
こうならないためにも、目先の労働力・費用などに囚われずに、従業員も会社も守れる対策をとる必要があるのです。


















