SES事業者への労働局の偽装請負調査で聞かれることと対応方法【2022年1月加筆】
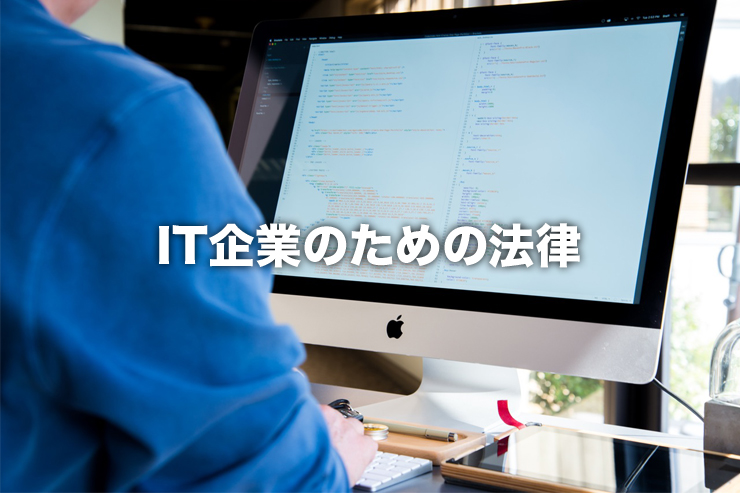
SES事業者には、定期的もしくは申告(いわゆる、通報・タレコミ)があれば、労働局の業務委託や派遣に関する適正運用や偽装請負等をつかさどる部署からその実態について、書類提出や面談形式の聞き取り調査などが行われます。
流れや必要な書類については、別の記事(SES事業者に労働局から調査の通知が来た場合の対処法)にも記載をしておりますが、大まかな流れとしては、面談調査の日程をあらかじめ労働局から決められ、事前にSES事業に従事する労働者一覧を送り、その中から2,3名分をピックアップされ、対象者の各種書類を、面談調査当日に担当官が各種書類を見ながら質問をしていくことになります。
書類の準備までなら自社内であらかじめ行えますが、調査当日のどんな質問をされるかまでは、経験をしたことがあるか、周りに経験者がいてその話を聞くかしない限り、なかなか情報が入ってきません。
今回は、SES事業における調査の際の調査当日には、一般的にどのような質問を受けるのかを複数の実例をもとに解説をしたいきたいと思います。
会社概要について
面接などと一緒で、自己紹介から行うことが一般的です。まずは、会社概要について少し細かいところまでの質問もしてきます。具体的には、次のような質問が多くあります。
- 事業形態やどういったものですか?
- その中でもメインの事業は何ですか?また、その割合は?
- 正社員と有期雇用契約の社員の割合は?
- 一般派遣の資格はお持ちですか?
- 派遣の受け入れはしていますか?
- 仕事を受託する方法は?
受託の方法などの質問は、作業者が自ら営業をし、その際に発注者からの面接などを受けていないかなどを確認していると考えられます。
業務委託の契約であれば、作業者の選任は受託者が行い、発注者は行えませんので、そのチェックでしょう。
多くの企業では、営業担当者もしくは事業主自らが受託することが通常かと思います。
各対象者の実態について
一通り会社の概要などを聞かれた後は、いよいよピックアップされた個別の労働者ごとの確認に入ります。
個別の労働者単位での確認、質問のため、企業や企業の中でもクライアントや担当の労働者ごとに質問は変わってきますが、概ね、以下のような質問をされることが多くあります。
- 発注の経緯は?
- 受注案件の把握の方法は?
- 当該案件に下請けはいるか?
- 就業地はどこか?
- 事前面談などはやっているのか?やっているのであれば、いつ、だれが、どんな話を?
- 社会保険、労働保険は加入しているのか?
- 就業先の部署やチームはどういう編成か?自社で把握しているのか?
- 現場のリーダーは誰か?
- 自社、クライアント双方に現場責任者などはいるのか?
- 指揮命令は、請負事業主もしくは現場責任者を経由して行われているか?(現場で直接の指揮命令は出ていないか?)
- 仕様書、指示書などはあるか?
- 業務の完了確認などはしているのか?
- 仕様変更などがあった場合はどうしているのか?
- 作業場所の状況は?(場所は分かれているか、名札や、ロッカーなどは?)
- 勤怠管理や休暇の許可はどの様に行うのか?
- 休暇について、クライアントへの報告や許可は必要か?
- クライアントに職務経歴書などは出しているのか?それはなぜか?
ここからは、かなり踏み込んだ質問をしてきます。主な焦点は、「指揮命令」と「労務管理」です。
現場のチーム編成、現場責任者の有無、仕様書・指示書等の有無、完了確認の有無、命令系統の確認などの質問は、主に指揮命令が現場で行われていないかの確認です。
責任者はいない、仕様書・指示書がない、となれば、現場での直接の指揮命令があるのではないかと疑われます。
後のクライアントに対する反面調査や、作業者本人への聞き取り調査などで直接の指揮命令が確認できれば、偽装請負の一部として是正の対象となるでしょう。
他には、労務管理・人員配置の方法などについてよく聞かれます。
自社の社員は、自社で管理する必要があるため、クライアントが管理・許可をしているなどということになれば、これも偽装請負の一部として是正の対象となるでしょう。
また、クライアント側による人員の選定はできないため、面談・面接などは必要ないのでは、というのが労働局の考えです。職務経歴書や決定通知書など、クライアント側が選定を行っていれば、これもまた偽装請負の一部として判断される可能性があります。
作業場所の状況については、指揮命令や労務管理ほど厳重な対策は求められませんが、労働局のガイドライン等では、直接指揮などが発生しないよう、クライアント社員と常駐の自社社員とを明確に区別できるような対策が施されていることが望ましいとしています。
申告(通報・タレコミ)調査の場合
いわゆる、通報やタレコミなどを元に行われる調査では、調査当日に提出する書類をあらかじめ通報者から得ていることや、場合によっては内部のマニュアルやメール等のやり取りの写しなど社内文書を通報者から得ている場合があります。
その様な場合、あらかじめ取得していた書類と当日受け取った書類との整合性についてや社内文書の事実確認などについて質問をされます。
内部情報などについては、個別の事案により大きく変わるため、労働局から質問をされた一例を紹介します。
- 社内マニュアルのようなものがあるのか?どういったものか?
- ○○という項目があるようだが、事実か?どういったものか?
- ××というルールは何のためにあるのか?
- 書類に関する質問では△△と回答していたが、メールのやり取りを見ると××となっているが、これはどういうことか? など
申告による調査特有の質疑では、調査全体の流れとして、まず提出された書類から精査し、その後に申告に関する部分の質疑に入ります。その際、労働局は通報者からあらかじめ情報提供があることを隠して調査を進めます。
そうすると、前半で提出書類を元にした質問の回答と、通報者から提供された情報に齟齬が出ることが多くあります。労働局としては、そういった部分をみて、隠蔽・虚偽などがないかを見ているのです。
話の齟齬について、後から取り繕うのはやはり怪しく見えます。事態の早期幕引きのためにも、事実を正直に答える方が良いと言えます。
前もって定期調査か申告調査かを判断することは事実上難しいですが、申告による調査の可能性もあることを考えておく必要があるでしょう。
その他(採用関係など)
稀に、直近の採用に関する事項を聞かれることがあります。事例としては、次のような質問がありました。
- 契約内容などは、あらかじめ明示しているか?
- SESを行う際の勤務地についてなどはちゃんと説明しているか?
- 固定残業制の者はいるのか?その人数は?
- 従業員から苦情などがあったことはあるか?
SES事業を行う場合、作業者は自社とは違う場合がほとんどです。その辺りがしっかりと明示されているかを見ている様です。
直接偽装請負に関連する部分ではありませんが、確認されることが多々あります。
調査の終了
上記のような確認・聞き取りを2時間ほどで行います。提出した書類は労働局が持ち帰りますので、写しを提供します。
是正の有無、内容については、後日書面で通知されます。
多くの調査では、反面調査と言って、クライアント側にも調査を行い、最終的に是正勧告を行いますので、是正の有無、内容については、1、2か月後に書面で通知されます。
当日は、これで終了です。
絶対にしてはいけないこと
他のSES関連記事(SES事業者に労働局から調査の通知が来た場合の対処法)でも記載しましたが、虚偽の回答・事実の隠蔽などは絶対にしないようにしてください。
虚偽の回答・事実の隠蔽などしても、反面調査や場合によっては労働者本人への聞き取りなどで、実態が明らかになります。
その場合、1回目の調査ではほぼあり得ない罰金や社名公表などの重い処分が、1回目から下される可能性が非常に高まります。
当然、後からバレても同様です。
まとめ
尋問のように質問攻めにされるわけではなく、あくまで内容と事実の確認という形なので、進みとしては和やかに進行することがほとんどですが、やはり、細かい所にも目を光らせています。
違反があったからと言って、直ちに罰金や社名公表ということではないので、悪い印象を持たれないよう、誠実に対応するよう心がけることが大切です。


















