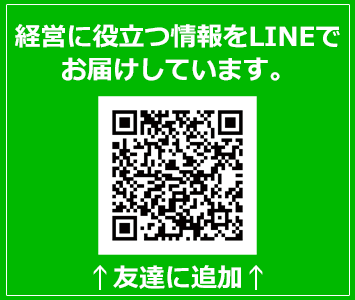2018年問題とは?会社が雇止めを行う際の注意点【弁護士の解説】
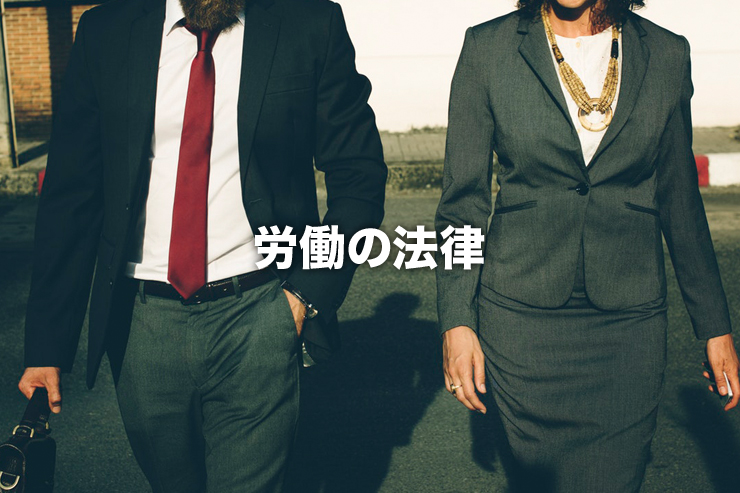
「2018年問題」会社が有期契約社員の「雇止め」を行う際の注意点とは
近年話題となっていた雇用関係における「2018年問題」。
雇止めトラブルが増えると予想されていましたが、トラブルとならない雇止めとはどういったものなのでしょうか。
労務問題は、
そもそも「2018年問題」とは?
2012年の労働契約法の改正により、2013年4月以降に契約締結した有期労働契約社員が、2018年4月以降から期間の定めのない無期労働契約社員へ転換を申し出ることができる「無期転換ルール」に関する法律が制定されました。
無期転換ルールは、通算5年を超えて契約される者が、6年目の契約以降に申込できる権利が発生します。対象社員から申込みがされると、会社側は承諾したものとみなされ、原則拒否はできないとされています。
そのため、会社側は直接雇用と同等の無期労働契約社員への転換の申込みをされないために、2013年4月以降の契約で6年目に突入する最初の年である2018年に、雇止めに関するトラブルが続出すると懸念された問題が、いわゆる「2018年問題」です。
では、その問題となる「雇止め」とは?
雇止めとは、一般的に、期間の定めのある社員(有期契約社員)を契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等、会社が契約の更新を拒むことを言います。
一時的な仕事や、季節的な仕事については、契約が更新されなくても「雇止め」とはなりません。雇止めを行うこと自体は、違法なことではありません。
しかし、雇止めの理由が、無期転換を回避するためのものであったり、客観的に見て不当なものといえる場合には、その雇止めが違法・無効と判断される場合があります。
雇止めが認められなかった場合
もし雇止めが認められなかった場合、会社側はどうなるのでしょうか。
次のような請求をされる可能性があります。
⑴雇止めの無効・撤回による継続雇用
雇止めが認められなかったため、契約は更新され、雇用が継続されることになります。
⑵雇止めとして働けなくなった期間の未払い賃金の請求
⑴の継続雇用とともに、本来の更新日以降について未払い賃金として請求されることもあります。
紛争が長引くほど、当然未払い賃金の額は増えていきますので、不要としていた人材の雇用継続の上、未払い賃金の支払いと一番コストのかかる結果かもしれません。
⑶通算5年を超える反復更新がある有期契約社員の場合、無期労働契約への転換
いわゆる無期転換ルールです。
2013年4月以降の有期労働契約で、通算5年を超える反復更新がある場合には、申込みがあれば無期労働契約への転換をしなければなりません。
雇止めが認められる場合
雇止めが認められるためには、次の要素が必要とされています。
⑴契約締結時に雇止めに関する事項を明示しておくこと
雇止めを行う可能性がある場合には、雇入れ時に、更新の有無、更新をする場合の基準などを契約書などに明示し、しっかり説明をしている必要があります。
これは、更新時も同様です。
⑵雇止めを行う際は、前もって予告をすること
3回以上の更新、通算1年以上の継続雇用、または、1年を超える契約期間の有期契約社員の雇止めを行う際は、契約を解除する30日前までに当該社員に対し予告をしなければなりません。
いわゆる、解雇予告に相当するものになります。
⑶雇止めをする理由を明らかにすること
雇止めをする社員から、雇止めの理由について証明書を請求された場合には、遅滞なくこれを交付しなければならないとされています。
「更新回数の上限によるもの」「担当業務の終了」「勤務態度の不良」など、契約期間の満了とは別の理由が必要とされています。
証明書を請求されなくても、雇止めを行うには理由が必要ですので、注意が必要です。
なお、雇止めの理由は、正当なものである必要があります。ここで言う正当とは、客観的にみて合理性があり、社会的にみて相当性があるかどうかで判断されます。
⑷契約期間への配慮義務
使用者は、1回以上の更新、かつ、1年を超えて継続雇用している有期契約社員との契約を更新しようとする場合には、契約の実態や当該社員の希望に応じて、可能な限り契約期間を長くするように努めなければならないとされています。
これらの手続きが行われていなかったからと言って、直ちに雇止めが違法・無効となる訳ではありませんが、適法・有効な雇止めを行う際には、必要な要素となってきます。
自社に契約社員がいて、雇止めを行う可能性があるのであれば、早めに、上記を含めた制度を作り、運用していくことが必要となります。
まとめ
2018年問題は、あくまで皮切りに過ぎず、「雇止め」の問題は、2018年以降も引き続いて発生するトラブルの一つであります。
期間が決められているからといって、必ずしも自由に雇止めが認められる訳ではないことを改めて理解し、有期雇用と言えども、しっかりと採用計画、社内運用を立てた上で、雇入れるようにしましょう。