自社ウェブサービスでユーザーの投稿トラブルを未然に防ぐ法的対処

事業に想定外はつきもの
事業には想定外のことがつきもの…私も法律事務所を経営していますが、つくづく思います。
特にIT・ウェブ事業者にとっては、進歩も速い分、想定外のことが起こるリスクが大きいのも事実。
そこで、インターネット事業者が想定外のことが起きたら、どう対処すればいいのかを解説していきます。
インターネット事業者、こんなときどうする?
自社のウェブサービスが、ユーザーによる投稿を受け付ける機能やSNSのような機能を持つ場合、
ユーザーが、以下のような投稿した場合は、事業者としてはどうしたらいいでしょうか。
・ユーザーが著作権を持っておらず、許諾も受けていないコンテンツを投稿する。
・他のユーザーや第三者を誹謗中傷する書き込みをする。
そんなのユーザー勝手にやったことだから、知らんがな( ̄▽ ̄)って言いたいですよね!
でも…それだけでは済まない場合があるんです…。
プロバイダ責任制限法では、ユーザーが他人の権利を侵害するコンテンツを投稿したことを知りながら、
事業者がその状態を放置していた場合には、事業者も、責任を問われる可能性があるのです。
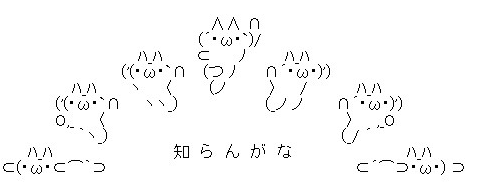
「知らんがな」は、通じない…
ユーザーにこのような書き込みをさせないために、事業者にできることは…
まずは利用規約に、禁止事項として
「ユーザーが、著作権侵害や名誉棄損にあたる表現の書きこみを禁止する」
旨の記載することが考えられます。
しかし、それでもユーザーが、上記のような書きこみをしてしまった場合は、
そのユーザー自身が責任を問われるのは当然ですが、
事業者までも権利侵害に関する責任を問われる可能性があるのです(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
インターネット事業者、じゃあどうする
つまり!事業者も、ユーザーが他人の権利を侵害する投稿であると知った場合においては、
削除などの対応を取らなければならないのです!
見て見ぬふりはできない…ってことなんです(  ̄0 ̄)/ピシ!!

見ざる、聞かざる、言わざる…
そうすると…他のユーザーや第三者から、権利を侵害している投稿があると通知されたら、
事業者としては問題になっている投稿を削除するという方法が考えられます。
そのためにも、利用規約等で
「事業者が権利侵害であると判断した場合には、ユーザーの投稿情報を削除することができる」
という規定を予め定めておく必要があります。
しかし…他のユーザーや第三者からの権利を侵害している投稿があるとの通知が、
間違っていた場合または嫌がらせ目的の嘘の通報であった場合には…
今度は投稿したユーザーから削除したことに対するクレームをされる可能性があります(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
まさに板挟み状態…(^^ゞ
そこで、事業者としては、
①第三者から権利侵害の通知があった投稿が、本当に権利侵害をしているかを確認する
②コンテンツを削除する場合は、誤申告であった場合に備えて、元に戻せるようにしておく
などの対応をしておくと安心です。
①問題のコンテンツが権利侵害をしているかを確認するって言っても…
権利を侵害しているか分からないよ…という場合には、
専門家である弁護士等に相談するのが得策です。
想定できるリスクには、適切に対処しておけるように、
万全の準備をしておきましょう(ロ_ロ)ゞ


















