従業員(業務委託先)が契約後に競業他社へ転職することをIT企業は防ぐことができるのか【2022年11月加筆】
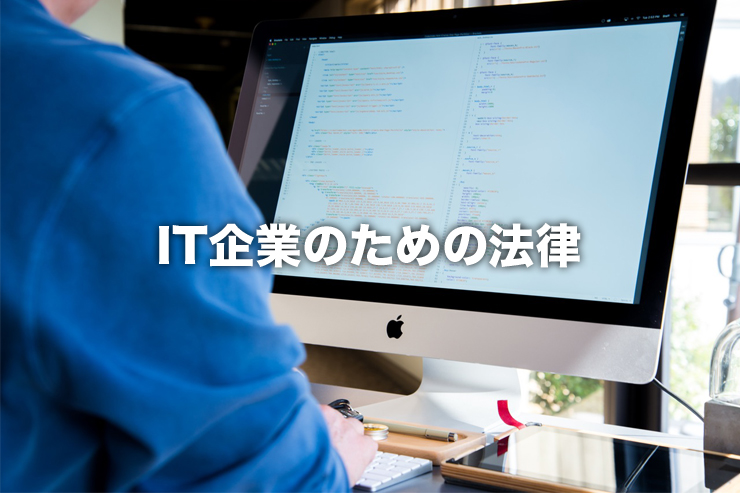
退職した従業員が競業他社に行くのを防ぎたい
IT業界は、人不足を言われて久しいのが現状です。どこの会社も、優秀な方を求めて、日夜奔走しています。
社員の引き抜き行為も日常茶飯事です。
IT業界に多い「従業員の引き抜き行為」法律では損害賠償などを請求できるの?
企業としては、自社の従業員が、競合他社に転職してしまうのを避けたいと考えるところも多いでしょう。
従業員が、自社の重要な営業秘密やノウハウなどを持ち出してしまうかもしれないですし、顧客なども奪われてしまうかもしれません。
企業としては、退職した従業員が、退職後に競業行為を行うと会社に重大なダメージが生じるおそれがあると考え、会社が競業を禁止する必要性を感じるのも当然でしょう。
一方、従業員側のことを考えると、まず憲法上、職業選択の自由というのが保障されています。
また、これまでのキャリアを使い、それを生かせる先として、競業他社に転職するというのは、合理的な選択です。よって、この会社側の言い分と従業員側の言い分が対立することになるのです。
退職した従業員と競業禁止の合意が必要
まず、会社の法で、従業員に退職した際には、競業他社に転職してほしくない場合には、会社と従業員とで、従業員が退職した際には、競業他社には行かないという合意が必要です。
そもそも、従業員側には、職業選択の自由が保障されていますので、会社となんの約束もないのに、競合他社に転職するなということはできません。
よって、会社と従業員で、競業他社には行かないという合意(競業禁止の合意)が必要なのです。
その合意を得るために、会社としては、従業員と契約書又は合意書を結んでおくことが必要です。
退職後の競業禁止の合意が有効と判断されるためには
一方、上記のような合意があれば、一律に禁止できるかというと、そんなことはありません。
従業員側にも、職業選択の自由がある以上、例えば、一生、競業他社に就職するなどの規定は無効になります。
それでは、どのような内容であれば、有効なのでしょうか。
有効と認められる競業避止契約の内容
- 競業避止義務期間が1年以内である(2年でも、有効とした裁判例あり)
- 禁止行為の範囲につき、業務内容や職種等などの限定が規定されている
- 代償措置(高額な賃金など「みなし代償措置」といえるものを含む)が設定されている
有効と認められない競業避止契約の内容
- 業務内容等から競業避止義務が不要である従業員と契約している
- 日本全国といった必要以上に広範囲な地理的制限をかけている
- 競業避止義務期間が2年超となっている
- 代償措置が設定されていない
以上のような条件を守っていかないと、競業禁止契約などを結んでも、無効になってしまう可能性があります。
業務委託先への競業禁止の合意は有効か
上記は、自社の雇用している従業員に対して、競業禁止が有効になるのかということでした。
では、雇用はしていないが、業務委託として業務を頼んでいる人にも、上記のような競業禁止の合意は有効にできるのでしょうか。
この点については、知財高裁平成29年9月13日判決があります。
事例としては、委託契約をしている方との間で、契約書内に「契約期間中及び契約終了後12か月間、A社の業務内容と同種の行為を行ってはならない」という趣旨の競業避止条項があったというもの。
「A社の業務内容」というのは「発注書に従いX社の企画に基づき、両者が協議して決定する仕様に基づく開発及び類似する開発に限る」という限定つきのものでした。
しかし、委託先の方が、競業避止義務に違反する開発業務に従事したので、A社が、上記競業避止条項に基づき業務を行うことの差止及び損害賠償等を求めたという事案です。
これに対して、知財高裁は、競業禁止条項の有効性を認め、競業避止義務違反を認めました。
その理由としては、以下のようなことを判示しています。
業務委託先の人が、A社のプログラマーとしてA社及びその顧客の営業秘密などを取り扱うことになり、業務委託先の人が、これらの営業秘密などを用いて競業行為を行うことによりA社に不利益が生じることを防止する必要あること。
契約終了後12か月、競業避止義務を課する規定は、十分合理性があり、許容範囲内である。
業務委託先の人は、ソフトウェアの開発責任者を務めるなど重要なポジションにあり、営業秘密に触れる機会も多かったことから、上記程度の制約はやむを得ない。
以上のように、企業としては、業務委託先の人(会社)にも、合理的な範囲内で、競業禁止の合意を有効にすることができるようになるのです。
まとめ
以上のように、企業としては、従業員や業務委託先に、競業禁止の合意をすることができます。
しかし、合意の内容を誤ってしまうと、合意自体が無効になってしまう危険性があります。内容については、十分に注意するようにしましょう!


















