スポーツテック(データ分析)に関する法律と注意点【解説】
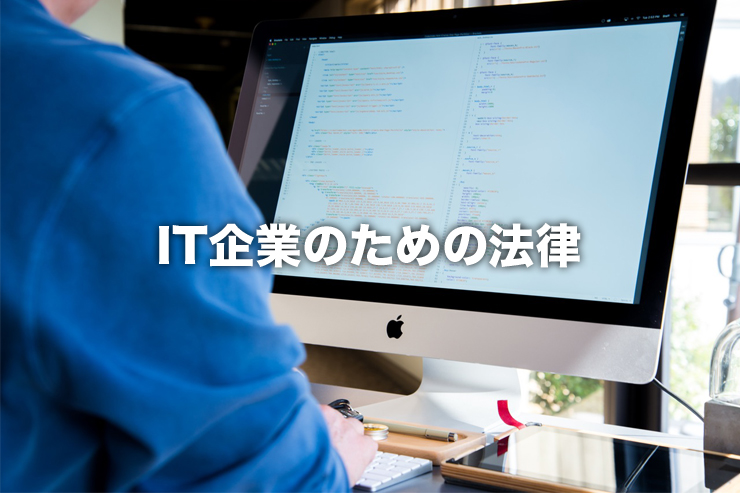
スポーツテックとは
スポーツテックとは、スポーツ×ITを組み合わせたテクノロジーのことです。
スポーツの世界では、対戦相手の分析などで、IT技術が駆使されていることが当たり前になってきていますが、それ以外にも、次のようなIT技術が活用され始めています。
- 選手のパフォーマンス改善やケガの予防
- チームの経営改革
- ファンの観戦体験の向上
このようなスポーツテックについて、現状、どのような法律になっているのでしょうか。
データ分析における法的問題
データは法律上、どういう位置づけなのか?
スポーツテックの分野では、データ分析が非常に重要になってきます。このデータについては、法律的に、どのような問題があるのでしょうか。
そもそも、「データ」のような形のないものは、法律上の所有権の対象ではありません。
そうすると、データについて、他人に奪われたり、無断で使用されたりした場合でも、データの管理者は、何もいえないのでしょうか。
そのため、このような民法上の所有権や占有権等の概念では法的保護は受けられないのが原則です。つまり、民法上、データそのものは、他人に奪われたり、不正に転用されたりしたとしても、自分の「物」のように、返せなどとは言えないということです。
データと著作権
著作権の対象となる「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。つまり、何かしら、人が創造し、オリジナリティが必要とされているのです。
スポーツに関連するデータ、例えば、選手につけられたセンサーや試合会場のトラッキングシステムについては、データ自体は、収集されたデータですので、オリジナリティがあるわけではありません。
よって、データ自体は、著作権で保護されるわけではありません。
もっとも、著作権法上、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」は著作物として保護されます(データベースの著作権)。
つまり、データを体系化し、構成したものについては、著作権で保護されるのです。イメージでいうと、プロ野球選手名鑑に掲載されている選手の体系化されたデータについては、著作権で保護されます。
このようなデータベースの著作権が認められると、このようなデータベースを勝手にパクられた場合には、その差止請求や損害賠償請求をすることができるのです。
データと特許権
特許権は、「発明」いえるものが対象となります。
「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。特許権の対象となるためには、「新規性」が必要であるとされています。
そうなると、データ自体に、特許権が認められる場合には、相当限定されると考えてよいでしょう。
データと不正競争防止法
不正競争防止法では、「営業秘密」があり、営業秘密を無断で持ち出すと、民事上、刑事上の責任が問われることになります。
この営業秘密ですが、自社がこれは「営業秘密だー」と思えばいいのではなく、法律上以下の要件を満たす必要があります。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
スポーツのデータについては、公開されていることも多いので、③非公知性が満たされないことも多いと思います。
もっとも、それらのデータをチーム内部で加工、分析したもので、内部で管理している場合には、不正競争防止法の対象になります。
不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すると、当該「営業秘密」を漏えいしたもの、勝手に使用している者に対して、侵害の差止、損害賠償請求などをすることが考えられます。
民法上の不法行為
データ自体が、上記のような法律で保護されないとした場合でも、一定の投資と労力を投じて収集・分析・加工されたデータを、無断でパクる行為は、民法709条の不法行為が成立しうるとされています。
これにより、パクッた相手方に、損害賠償の請求などをすることが考えられます。
データと個人情報保護法
スポーツにおけるデータについては、選手の身体的なデータ、過去の経歴、運動中の心拍数、メンタルチェックなどの個人に関わるデータを扱うことになります。そこで、問題となるのが、個人情報保護法です。
個人情報とは、簡単にいうと、個人を特定できる情報を全てをいいます。
選手達の氏名、身体データ、出身校などの情報は、「個人情報」に該当します。個人情報に該当すると、個人情報保護法が適用されます。
個人情報保護法が適用されると、次のことを行う必要があります。
- 安全管理措置
- 第三者提供に関するルール
- 開示請求への対応
個人情報保護法については、改正法が、2017年5月30日に施行されています。
個人情報の取得
事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定する必要があります。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされています。
多くの事業者は、プライバシーポリシーという形で、個人情報の取り扱いに関する規定を作成していると思いますが、そこに「利用目的」という項目があるはずです。
「利用目的」をきちんと特定する必要があるため、作成していない場合には、早急に作成してください。
では、どの程度「特定」する必要があるのでしょうか?これは、普通の人が、「利用目的」を見た場合に、個人情報が何に使われるのか分かる程度に、具体的に記載する必要があります。
例えば、「利用目的」として「当社事業目的のため」「当社マーケティングのため」というのは、NGです。なぜなら、何に利用されるか、分からないからです。
「DM、メールマガジンを配信するため」、「問い合わせに対応するため」など、一見して何に使われるのかが分かるように、記載する必要があります。
利用目的の通知・公表
個人情報を取得する場合には、予め利用目的を通知・公表しなければなりません。
多くの会社は行っていると思いますが、プライバシーポリシーなどは、ウェブサイト上や申込フォーム上に、掲載しておく必要があります。
個人情報の安全管理措置、従業員や委託先も監督
事業者は、集めた個人情報を法律に則り、安全に管理する必要があります。
では、具体的に、どのように管理すればよいのでしょうか。これには、個人情報保護委員会から、ガイドラインが示されています。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
ただ、この資料は約100ページにも及ぶ膨大な資料です。読みこなすのも大変だと思うので、次回以降、改めて解説します。
また、事業者は個人データをクラウドサービスに預けてる、他の事業者に預けている場合には、その委託先も監督しなければならないとされています。
第三者提供の制限
事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、第三者に個人データを提供してはならないとされています。
例外としては、(1)法令に基づく場合(2)オプトアウトなどの場合があります。
個人情報の開示、訂正、利用停止
事業者は、本人からの求めがあれば、個人情報は開示しなければなりません。また、個人情報に誤りがあれば、本人からの求めに応じて、調査し、訂正しなければなりません。
さらに、個人情報を法の義務に違反して取り扱ってるときは、本人からの求めに応じて、利用停止等を行わなければなりません。
要配慮個人情報について
また、スポーツ関連のデータについては、選手たちの病歴に関わる情報や、健康状態のデータなどが含まれます。
これは、個人情報保護法の「要配慮個人情報」に当たります。要配慮個人情報を取得するには、原則として本人の同意が必要となります。
また、要配慮個人情報を第三者に提供するに当たっては、必ずあらかじめ本人の同意を得る必要があります。オプトアウト方式での第三者提供は認められていませんので注意が必要です。
匿名加工情報に関する加工方法や取り扱い等の規定の整備
匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報です。
これは、個人情報には該当しないことから、本人の同意なしで第三者に提供することが可能で、これらをビッグデータとして活用されることが期待されています。
この匿名加工情報を作成した事業者には、以下のような義務が生じます。
- 匿名加工情報の適正加工義務
- 漏えい防止措置義務
- 作成したときの公表義務
- 第三者提供をする場合の公表・明示義務
スポーツテックの法律には注意を
スポーツテックは、これからの分野であり、法律も未整備な部分があります。
データの取り扱いには、法律が重要になってきますので、十分に注意しましょう。


















