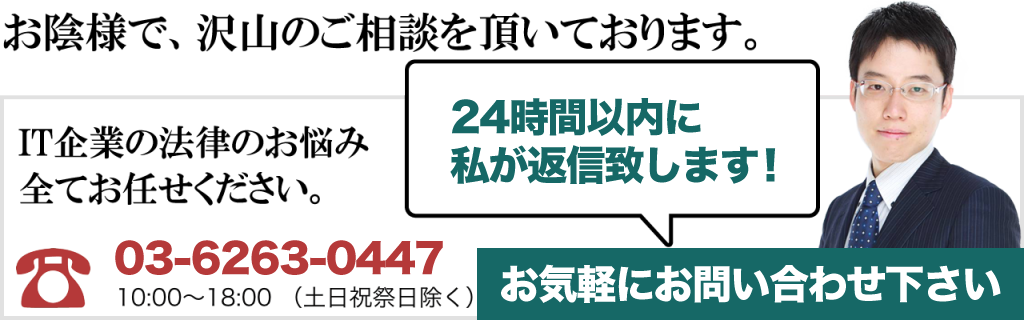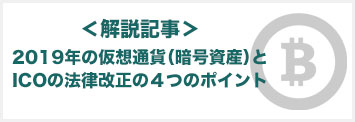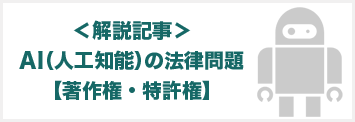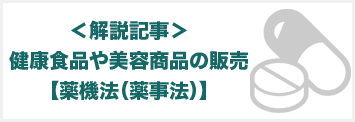SaaS系のスタートアップ企業が、特許権侵害をされたときの対処法【2022年7月加筆】

SaaS型企業が特許権侵害を主張するために
SaaS(Software as a Service)系のスタートアップの場合、他社が自社サービスと類似したサービスを見つけた場合に、どのように対処していくかは非常に重要です。
つまり類似サービスが出てきたときに問題になるのは、それが権利の侵害を立証するかという点に特に留意する必要があります。
そこで、(1)権利侵害といえるか、(2)創り込んだ権利を前提に、裁判上いかに侵害を立証するかという各点について検討します。
いかなる権利侵害というか
SaaS系のスタートアップの場合、特に特許戦略をいかに構築するかについて、注意すべきポイントはいくつかあるのですが、自社の特許権が侵害されたときの対応を考えてみたいと思います。
SaaS系の場合、クラウドでソフトウェアを提供し、ユーザー側でソフトウェアをインストールするのではなく、ベンダー(プロバイダ)側でソフトウェアを稼働させ、ユーザーはネットワーク経由でソフトウェアの機能を活用することとなります。
SaaSサービスを提供する場合、その構成の全てを明らかにすることは簡単ではありません。
そのため、類似したサービスを使用することで確認できる構成を起点として、いかに侵害立証できる権利を構築することができるか、という点が重要な課題になります。
例えば、SaaSの場合、サービスがクラウドで提供される以上、基本的には、UIに現れる挙動しか確認できないため、UIに現れる挙動から確認又は推認できる構成をもって、侵害を立証できるように権利を特定していくことが考えられます。
その際には、裁判でいかなる立証手段を用いて、いかに立証していくかの見通しを立てておくことも重要といえると言えます。
裁判上の立証手段―書類の提出命令・査証制度―
上記の権利侵害については、裁判上の制度を利用して、明らかにすることができます。
例えば、侵害立証のための書類提出命令制度です。
これは、相手方に、そのSaaSサービスがどのような仕組みになっているかを裁判所に提出させる制度です。この制度は、常に認められるわけではなく、「正当な理由」がある場合に認められます。
また、もうひとつの方法として、査証制度が挙げられます。
これは、実際に専門家が、サービス内容について、直接調査して、特許権侵害があるかを見る制度です。
侵害行為の立証のための書類提出命令について、裁判所はこれらの手続を利用することに慎重で、実務上、積極的に活用されてきたとはいえない状況にありました。
他方、海外では、例えば、幅広く資料提出が強制される米国のディスカバリーや、英国のディスクロージャー、ドイツやフランスの査察制度等、日本よりも強力な証拠収集手段が用意されている国が少なくありません。
そこで、令和元年改正法では、権利者がより侵害立証をしやすくなるよう、「査証制度」が導入されることとなったのです。
この査証制度について、裁判所は、以下の要件を満たす場合に、査証命令を出すことができるとされています。
- 特許権侵害訴訟(又は専用実施権侵害訴訟)における申立てであること
- 相手方が書類等を所持・管理していること
- 立証のため証拠収集が必要であること
- 侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 他の手段では証拠収集ができないと見込まれること
- 相当でないとは認められないこと
改正の経緯も踏まえれば、査証制度が積極的に活用されていくことが期待され、今後、知財戦略を構築するにあたり、本制度を利用して立証していくことが有効だと思います。