資金調達の手段としての合同会社の社員権スキームの法律的な注意点【2023年5月加筆】
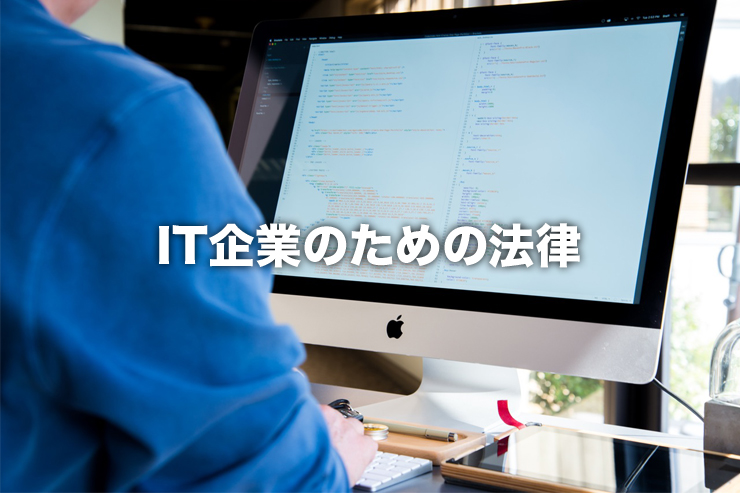
合同会社の社員権とは
合同会社の社員権とは、株式会社でいう株式のことです。
「社員」と聞くと、従業員のことを思い浮かべるかもしれませんが、その社員ではありません。合同会社の「社員」は、株式会社の「株主」だと思ってください。その会社の所有者という意味合いです。
【2023年5月現在】
多数の企業様から問い合わせを頂いており、現在までに39社の企業様の合同会社の社員権スキームの支援を行い、現在も5社の運用サポートをしております。
2022年9月の新たな法規制対応にも対応しています!
YouTubeで解説しています!
資金調達手段としての合同会社の社員権スキーム
多数の者から、資金調達をする場合には、原則として金融商品取引業の登録が必要です。例えば、会社の株式や社債などを多数人に対して売る場合です。
しかし、合同会社の社員権を、自ら販売する場合には、金融商品取引業の登録が必要がありません。そのため、資金調達の手段として、合同会社の社員権販売が行われているのです。
合同会社の社員権募集スキームのメリット
金融商品取引業の登録が必要ない
上記のように、合同会社の社員権の募集行為をする場合には、金融商品取引業の登録が必要ありません。
金融商品取引業の登録については、数ある許認可の中でも、取得が非常に難しいです。近年では、大手の資本が入っているなどの事情がない限りは、スタートアップ・ベンチャー企業が登録されるのは、ほぼ不可能です。
しかし、上記のように、合同会社の社員権募集スキームであれば、金融商品取引業の登録が必要ないという大きなメリットがあります。
【2022年6月加筆】
証券取引等監視委員会から、合同会社の社員権スキームについて意見が出されました。
この中でも、合同会社の従業員による当該合同会社の社員権の取得勧誘は金融商品取引業に該当しないことが明記されています。ただし、外部の代理店などを使って勧誘する場合には、金融商品取引業に該当し登録が必要です。
また将来的には、法改正により、合同会社の業務執行社員以外の者(従業員や使用人)による合同会社の社員権の取得勧誘金融商品取引業の登録が必要とされる可能性もあります。
新たな法律規制が!【2022年9月加筆】
2022年9月に、金融商品取引法の内閣府令改正されました。
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
これによると、合同会社の社員権は販売を勧誘する際に、業務執行社員が社員権の販売勧誘する場合には、従来通り、金融商品取引法の登録は不要です。
しかし!従業員や代理店などを使い、合同会社の社員権を販売勧誘する場合には、金融商品取引法の登録が必要になりました。
これは、2022年10月3日から施行されます。
これからは、法律的な観点からの整備が非常に重要になってくるといえます。
必ず合同会社・社員権スキームの法律に精通した専門家にご相談ください。
多くの者から資金調達ができる
金融商品取引業の登録の登録なく、資金調達する方法として、少人数私募債での資金調達があります。
一方で、勧誘する人数が49名まで(購入できる人ではなく、声掛けできる人が49人以下)に限定されていることから、多数人を対象にした大規模な資金調達は難しいです。
一方、合同会社の社員権募集スキームの場合、勧誘する人数に制限はありません。
また、実際に投資する人数にも制限はありません。
ただし、投資家から集めた資金を株式やFX等の有価証券に投資する場合には内国有価証券投資事業の権利等に該当しますので、500名以上の募集に該当する行為を行う場合には、有価証券届出書の提出等の開示義務を負います。
なので、この場合には、499人までの出資者にしておくのがよいでしょう。
そのため、勧誘ベースで49人までが私募となる株式や社債の自己募集と比べて、多人数の投資家に社員権を取得させることが可能です。
そうなると、大規模な資金調達が、金融商品取引業の登録がなく、出来てしまうのです。
合同会社の社員権募集スキームの問題点
合同会社の社員権は、株式会社でいう「株式」であると話をしました。社員権を持つ人は、会社の株主と同じ立場で、会社の方針に口を出すことができるということになります。
会社としても、運営方針に口を出されるのは本意ではないしょうから、その場合には、社員権の議決権を制限することが必要になります。
しかし、完全無議決権にしてしまい、資金調達をすることは、国民生活センターから、「定款上、出資者の議決権を完全に排除する場合、集団的投資スキームに該当しうる」との見解が示されています。
金融庁は、社員権募集スキームは、「合同会社の実態がない場合には、集団投資スキームに該当する」との見解を明らかにしています。
このように、ただ、合同会社を作り、社員権を募集すればOKというわけではありませんので、スキーム作りには十分注意してください。
合同会社の社員権募集スキームの注意点
合同会社の社員権スキームを使って、資金調達をする場合には、会社として以下に注意する必要があります。
社員が死亡した場合の取り扱いが、相続人が持分を承継するという文言を入れてしまうと、持分の評価方法が持分の払い戻しの際の計算ではなく、非上場株式の評価となってしまい、税額が高額になる可能性があるので、注意してください。
また、特定商取引法にも注意が必要です。
合同会社の社員権スキームは、金商法の対象外ですが、特定商取引法の対象にはなっています。
なので、合同会社の社員権の訪問販売や電話勧誘等の形式での販売にあたっては、書面の交付、クーリングオフ等の特定商取引法に定める規制に従う必要があります。
これを守っていないと、刑事罰等になることもありますので、十分注意してください。


















