暗号資産(仮想通貨)の法律改正で、ICO・STO(セキュリティトークン)の規制はどうなるのか
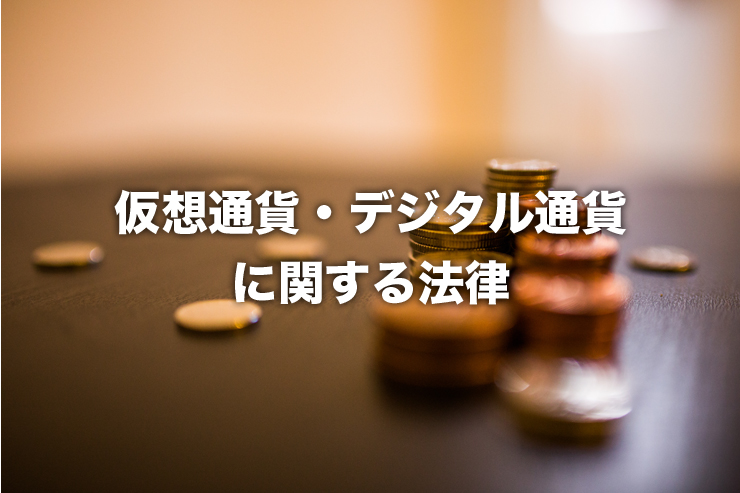
金融商品取引法の改正
2019年5月31日、暗号資産(仮想通貨)に関する法律改正が成立しました。
この中で、ICOについての規定がどうなったのかについて、解説します。
セキュリティトークンのICO(STO)が、金商法の対象に
金融商品取引法の改正では、新たに「電子記録移転権利」という概念を規定しました。これは、金商法に規定されている権利を有したトークンを意味しています。
この金商法に規定されている権利を有したトークンの代表例が、収益分配型のトークン、いわゆるセキュリティトークンです。
- 出資者が金銭等を出資
- 事業者が、出資された金銭等を充てて事業(出資対象事業)が行われ
- 出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該事業に係る財産の分配を受けることができる
このような集団的投資スキームにあたるようなトークンについては、「電子記録移転権利」に該当することになりました。
そして、このようなセキュリティトークンを販売する場合(ICO・STO)には、第一種金融商品取引業の登録を受けることが必要となります。
ただし、いわゆるクラウドファンディングの方法による電子記録移転権利の募集の取扱い又は私募の取扱いのみを行う場合には、第一種少額電子募集取扱業務を行うものとしてその登録要件が一定程度軽減されます。
この方法によりICO(STO) を実施する場合には、発行価額の総額が1億円未満であること、電子記録移転権利を取得する者が払い込む額が 50 万円以下であることという制限があります。
セキュリティトークンを販売する場合の手続規制
電子記録移転権利が開示規制の適用対象とされたことにより、セキュリティトークンを販売する場合には、原則として、有価証券届出書を提出し、目論見書を作成することが義務付けられます。
電子記録移転権利の募集及び売出しに係る有価証券届出書及び目論見書の記載事項を定める内閣府令の詳細は現時点では不明ですが、現在のホワイトペーパーで説明される事項を質的・量的に大幅に上回る情報開示が求められることが必要となることは間違いないでしょう。
これらの開示義務を回避するためには、セキュリティトークンを販売する場合においては、適格機関投資家私募や少人数私募の方法により行うことが考えられます。
また、セキュリティトークンの販売したとき、有価証券届出書を提出した事業者は、原則として、事業年度ごとに有価証券報告書を、半期ごとに半期報告書を提出することが義務付けられます。
ところで、セキュリティトークンを金商法改正法施行前に実施した場合でも、その後いずれかの事業年度末日におけるトークンの所有者の数が、1000以上となった場合には、その事業年度を含めて、今後5年間は有価証券報告書及び半期報告書を提出する義務が生ずることに注意が必要です。
ユーティリティトークンICOについての法律的規制
一方、ユーティリティトークンのICOについては、今回の法律改正で、金融商品取引法の対象にはなりませんでした。
この点については、従来通り、仮想通貨法(資金決済法)で、規制されることになります。
ICO・仮想通貨(暗号資産)の法律的規制について、日本法人と海外法人で合法的に行う方法とは【2019年5月31日加筆】


















