ブロックチェーン技術に関する開発契約・ライセンス契約・保守契約とは【解説】【2022年12月加筆】
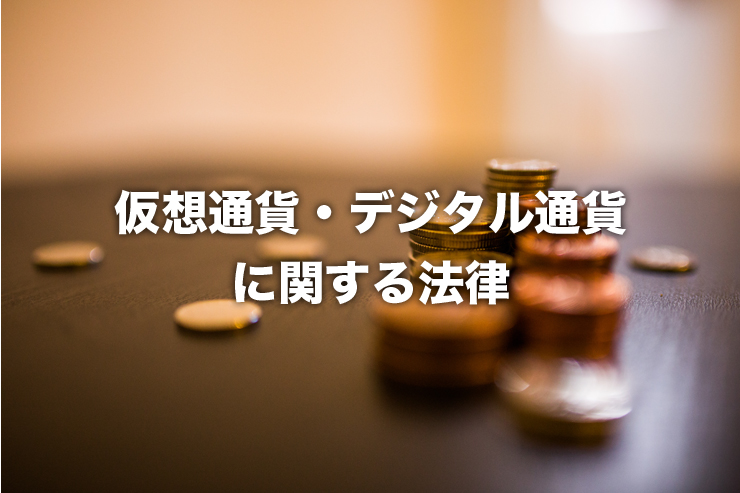
ブロックチェーン技術のライセンス契約
ブロックチェーン技術にまつわる契約関係について、解説します。
例えば、ブロックチェーンに関するソフトウェア等をダウンロードして利用したり、当該ブロックチェーンからサイドチェーンを作ったりする場合には、当該ブロックチェーン技術について、ライセンス契約を締結することが考えられます。
この場合には、ブロックチェーン技術を使用しているからといって、通常のライセンス契約と何ら変わることはありません。
しかし、ブロックチェーンに関わる部分については、次のことに注意が必要です。
ライセンス範囲の明確化
ライセンス対象となる技術を明確に契約で定めることが重要です。
ライセンシーとしては、自社で提供しようとするサービスの提供に必要な技術についてすべて許諾を受けなければ、サービスを提供できない可能性があります。
ライセンサーとしても、ライセンス料は、ライセンスする技術に応じて決定するので、ライセンスする技術を明確化する必要があります。
ライセンス料を決定方法は、以下の方法があります。
- 固定の金額の支払う方法
- 売上の●%という方法
- 上記の両方
契約期間
契約期間については、通常一定の期間が定められることが多いです。
しかし、ブロックチェーンサービスの場合には、半永久的なサービスが想定されることもあるため、契約期間を定めないこともありえます。
ブロックチェーン開発に関する契約
例えば、ブロックチェーンを利用したアプリケーション開発を行う場合に、アプリケーションの開発を外部の会社に委託することになります。
この場合には、通常のソフトウェアの開発委託契約と同じですが、以下の点に注意する必要があります。
システムの仕様
ブロックチェーン技術については、まだまだ確立していない部分もあり、仕様について最初に全体を設定することが困難なケースも多いです。
そのため、開発の進め方としては、ウォーターフォール型ではなく、 アジャイル型開発の方がスムーズにいくと思います。
責任の範囲
ブロックチェーンは改ざんがしにくく、ユーザーの損害等の問題は起こりにくいのですが、分散型システムなので、参加者が多く、また、ブロック上のデータが、チェーンによりつながっていくという特徴があります。
万が一、いったん問題が起きると、ブロックでつながっているデータすべてに影響が及ぶという可能性があります。
そのため、システムに瑕疵が存在していた場合、その損害の範囲が無数に広がっていく恐れがあります。
ベンダ側としては、損害賠償の上限を規定する(受領した金額等に責任を限定)ことが考えられ、ユーザ側としては、そのような限定をしたくないと考えるでしょう。
ブロックチェーン技術の保守管理
ブロックチェーンを使ったアプリケーションに基づくサービスをユーザーに提供しようとする事業者が、当該アプリケーション等の保守管理を委託する場合、保守管理委託契約を締結することになります。
この点、注意すべき点は以下の通りです。
保守業務の内容
ベンダとしては、保守業務として、どの範囲まで行うのかを明確にする必要があります。
ブロックチェーン・ビジネスが自体が発展途上な部分があり、保守改修が多くなる可能性があります。
契約では、どこまでのことをするのかを明確にしないと、無限に保守管理しなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。
保守委託料
委託料については、月額固定の金額で設定されることが多いです。
もっとも、ブロックチェーン・ビジネスにおいては、膨大なデータが集まるため、当初想定していた以上の保守管理がかかる可能性があります。
よって、ベンダとしては、一定の業務を超えた場合には、追加料金を設定することも考えられます。


















