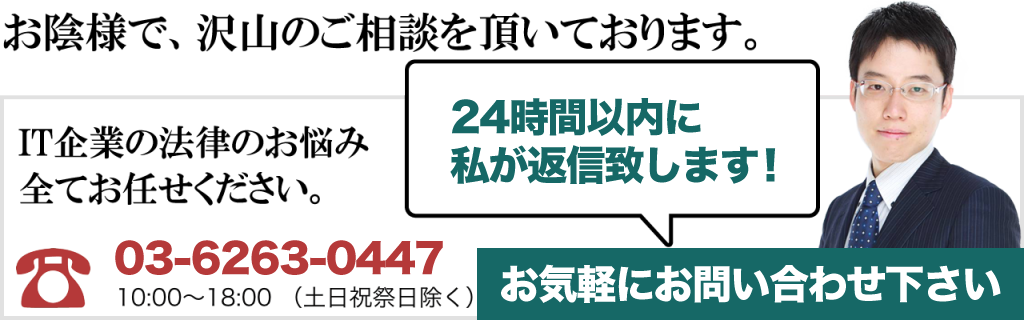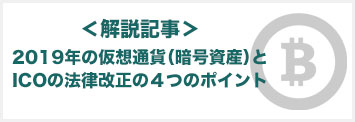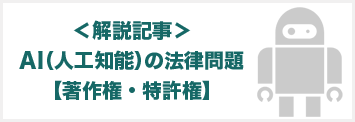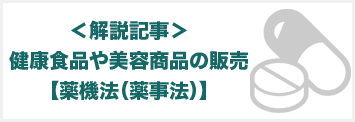システム開発でプロジェクトがとん挫した場合の法律的な検討事項【2022年12月加筆】

システム開発で、プロジェクトがとん挫した
システム開発プロジェクトが途中で頓挫した場合、ユーザがベンダに対して、金銭などの請求をすることが多いです。
その場合に、ベンダ側、ユーザ側の担当者が検討すべき事情について、解説します。
ベンダが納期になっても成果物を納品できない場合、ユーザはベンダとの契約を解除した上、前払いで支払済みの開発委託料の返還を求めることがあります。
ユーザがベンダに請求する金銭としては、支払済みの開発委託料及び年6分の金銭を請求することが考えられます。
誰のせいで、プロジェクトがとん挫したのか(帰責性)
プロジェクトがとん挫したことを理由に契約の解除を主張した場合、問題になるのは、ユーザ側とベンダ側、どちらのせいで、プロジェクトがとん挫したのかです。
ペンダが成果物の完成を遅延し、納期を遵守することができなかった場合でも、ベンダのせいではない場合、その責任を負わないことになります。
特にシステム開発は、共同作業的な面が多々あり、ベンダではなくユーザのせいで、ペンダが納期を遵守できない場合もあります。
プロジェクトがとん挫したのは、どちらの責任かが問題になります。
具体的には、ペンダ側としては、ユーザのせいであると主張立証する(協力義務違反等)
ユーザは、ベンダの帰責事由(プロジェクトマネジメント義務違反等)を主張・立証することになります。
システムのソフトウェア開発やアプリ開発で紛争になる法律的問題点をIT弁護士が解説
ユーザが、ベンダとの契約を解除できるのは、どの範囲?
ユーザ側担当者としては、ベンダ側に損害賠償などの請求する場合に、契約を解除できる範囲についても検討しておく必要がああります。
例えば、請負契約を解除した場合に、請負契約の全体が消滅したと考えてよいかという問題があります。
例えば、同じ請負契約でも、建築工事の場合、発注者が工事業者Aとの契約を解除した後に、工事業者Aの作業(既施工部分)を前提として工事業者Bが工事を完成することがあります。
このような場合、未施工部分のみ契約解除でき、既施工部分は契約解除できないとするのが一般的な考え方で、最高裁判所判例もそのような判示しています。
この判例では、「工事内容が可分」であることと、注文者に「既施工部分の給付に関し、利益を有する」ことを要件として、解除が制限されるように判示されています。
このような一部解除の問題については、システム開発プロジェクトでも問題となります。
建築工事の場合には、工事業者Aの作業(既施工部分)を前提として工事業者Bが工事を完成可能な場合が多いのに対し、システム開発プロジェクトの場合には、ベンダAの作業を前提としてベンダBがこれを引き継いで情報システムを完成させることは困難であるという事情があります。
そのため、例えば、ベンダの債務不履行を理由とする解除の場合と、ユーザの自己都合解除の場合に分けて、後者の場合には、損害賠償の算定として「ベンダーがそれまでに投入した 開発費用を工数計算(人/月)に基づいて算定する方法」を取ることが、裁判所でも言及されています。
このような請負契約の一部解除の問題は、比較的小規模なシステム開発プロジェクトでよく見受けられます。
小規模プロジェクトでは、契約自体は1つであるが、各段階に分けて、検収する仕組みが採用され、検収の度に、一定の金銭の支払義務が発生することを契約上定めていることがあります。
このような場合、後続の工程で債務不履行があり、契約解除となった場合に、すでに検収済みの工程まで解除の効力が及ぶのかという形で問題となります。
例えば、東京地裁平成25年7月18日判決では、次のような判決がでています。
裁判例本件請負契約においては、報酬支払期限は分割検収と定められ、各工程であらかじめ定められた納品物の対価として、納品物の検収の翌月末日までに、各工程に応じた報酬を支払うものと定められていたことが認められる。
そうすると、各工程の納品物(目的物)が完成し、検収を受けて引き渡されている以上は、その工程に関しては、原則として、本件解除の効力は及ばず、また、そうでなくても、解除時点で既に完成し引き渡された部分に関しては、解除の効力は及ばないと解するのが相当である。
システム開発紛争は、どこまで請求できるのかを把握する
上記のように、システム開発紛争は、訴訟になった場合、どこまでの金額を請求できるのか、請求される可能性があるのかを検討することが必要です。
それを踏まえて、相手方にどのような要求をするのか、要求された場合に、どのような対応をするのかを検討する必要があるのです。