AIやIOT、ウェブサービスの「データ」は誰のもの?帰属先は?
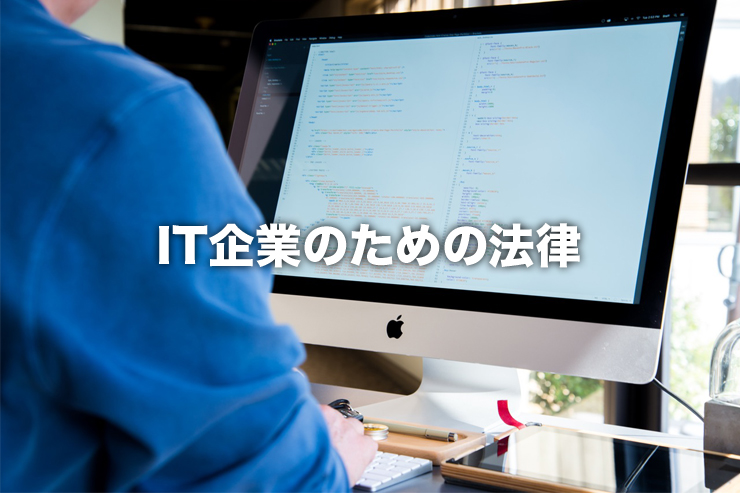
AIやIOTなどのデータは、誰に帰属するか?
データ取引についての契約において、データが誰に帰属するのかが問題となる場合があります。
例えば、機器メーカが、ユーザに販売した機器から測定される稼働データを取得し、機器の保守管理や新型機の開発に利用する場合など、多数のユーザからのデータを収取して外部に販売するような場合に、稼働データは、ユーザと機器メーカのいずれに帰属するのでしょうか?
また、ユーザや機器メーカは、相手方の同意を得ないで、自由に稼働データを利用したり、第三者に販売することは可能なのでしょうか?
この点について、ユーザとしては、機器メーカが、稼働データを機器の保守管理や新型機の開発に利用するだけであれば許容できるかもしれません。
ただ、稼働データを他の目的で利用したり、第三者に提供するということであれば、かなりの抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。
現にアクセスできる者は、法律上は、データを自由に利用できるものであり、その結果、現実問題としては、契約に定めがない限り、データを自由に利用できます。
また、ユーザも、稼働データに現にアクセスできるのであれば、法律上は、契約に定めがない限り、稼働データを自由に利用できることになります。
しかし、ユーザが稼働データにアクセスできない場合には、現実的には稼働データをそもそも利用することができません。そのような場合に、ユーザが、機器メーカに対して、稼働データを引き渡せと請求することができるのでしょうか?
この問いに対しては、データは、基本的には、誰に帰属するものでもない以上、ユーザには、契約で定めていない限り、機器メーカに対して、稼働データの引渡しを請求する法的権利は有しません。
ユーザは、自分が機器を動かしている以上、稼働データは、自分か権利者であるという気持ちをもつのが自然でしょうが、法的には、このような結論となってしまうのです。
法律的なデータの帰属先
世間一般的には、データに現にアクセスできる者を「帰属先」と考えていることが多いと思います。
確かに、データに現にアクセスできる者は、そのデータを他者と共有するまでは、そのデータを自らの意思のみでコントロールできるという意味で、帰属先・処分権者と同じような立場に立っています。
しかし、データを他者に開示した場合や、複数当事者が共同してデータが創出するような場合などは、結局誰が誰のものなのかが不明になってしまいます。
このような場合には、データに現にアクセスできる者同士で、当事者間で契約をすることによって、データの帰属先を決めることが可能です。
当事者は、あるルールを合意すれば、そのルールに拘束されることになります。言い換えれば、契約で定めた場合にはじめて、データの帰属先や処分権者という概念が生まれるのです。
このように、無体物であるデータについては、そもそも所有権という概念はなく、また、契約前には、知的財産権が成立する場合などを除き、帰属先・処分権者が決まっておらず、契約によって帰属先・処分権者を新たに創り出すという意味がある点で、通常の権利とは異なるのです。
データの帰属先を決める意味
では、契約によって、データの帰属先・処分権者を規定するということはどのような意味があるのであしょうか。
これは、契約の規定次第ですが、一般的に、データの帰属先・処分権者を規定するのは、データの処分権や収益を特定の者に集中させるという趣旨であることが多いといえます。
データの利用の方法としては、使用・複製・改変・2次利用・目的内利用・目的外利用などさまざまな形態があり得るが、あらゆる事態を想定して利用形態のすべてを契約に網羅的に規定することは困難です。
また交渉対象が増えて手間もかかるため現実的ではありません。
特に、ビッグデータ時代には、当初には想定していなかった用途でデータが利用されることもあるが、契約締結時に想定できない以上、契約書に規定できないし、また、あらゆる利用形態についてあらかじめ具体的に規定することは現実的ではありません。
そこで、「ある者にデータを帰属させる」「ある者にデータの処分権を与える」と契約で定め、特定の者にデータについての包括的な処分権限をもたせることで、将来、契約で規定していない事項について何らかの判断が必要となった場合には、その者に判断させることは、契約条項としては合理的といえます。
また、別の方法として、「当事者の協議によって定める」という方法もある。この協議方式は、当事者が納得しやすいというメリットがあるが、当事者の利害が対立する場合や当事者が不合理な行動をする場合には、デッドロックに陥る危険性があるというデメリットがあります。


















