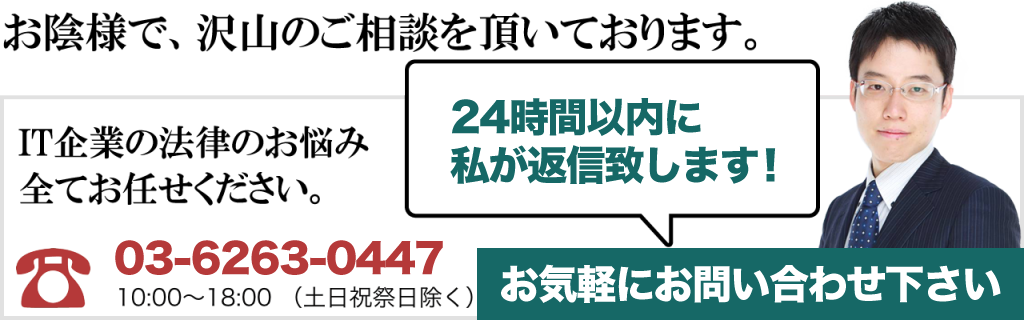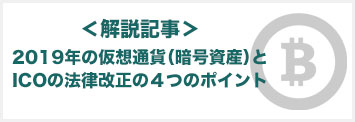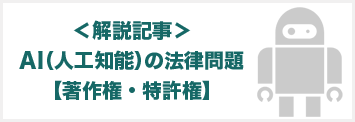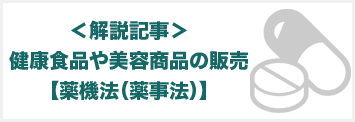システム開発におけるプログラムの著作権は「誰のもの?」【2024年2月加筆】

システム開発のプログラムの著作権は、誰のもの
システム開発においては、プログラムなどのコンテンツに関する著作権などの知的財産権についての帰属について、よく問題になります。
プログラムの著作物によく問題になるものとして、次の2つが挙げられます。
- ベンダとユーザー間で、プログラムに係る著作権の帰属が争われるケース
- 機能が類似するプログラムについて、著作権(複製権又は翻案権)侵害に当たるか否かが争われるケース
例えば(1)の類型は、著作権の譲渡を受けたと思い込んでいたユーザが、プログラムを利用(複製・改変等)していたところ、ベンダから著作権侵害だと言われたという事例が考えられます。
また、(2)の類型では、退職した従業員が、その会社に所属していた際に開発していたソフトウェアと同種のソフトウェアを開発したところ、元の会社から著作権侵害で訴えられたという事例が考えられます。
このような場合、法律上は、どのような権利関係に立つのでしょうか?
システム開発・プログラムの著作物の帰属
まず、システム開発におけるプログラムの著作権は、手を動かした人に原始的に権利が帰属します。この著作権を譲渡してほしい場合には、当事者間の合意(契約)によって権利を移転させることが可能です。
したがって、権利の帰属が争われた場合においては、次の順で検討する必要があります。
- そもそも、誰に権利が帰属するのか
- 著作権移転に関する合意はあるか
特に、会社の元取締役、元従業員との間で生じる紛争については(1)の点が主な争点になります。
一方、開発を委託したユーザと、受託したベンダとの間で生じる紛争については、(2)移転の合意が主な争点になります。
そもそも誰に権利が帰属するのか
システムを構成するプログラムは多数の作業者が分担して開発することが多いため、争いとなっているプログラムの作成者を調査・特定する必要があります。
この場合、開発会社の作業スケジュールにおける担当者の欄や、ソースコードのコメント欄に記載された作成者といった情報に基づいて特定することになります。
また、プログラムは何度も修正、改変を繰り返される。そのため、問題となったプログラムに複数の者による編集が加わっている可能性もあります。
この場合、関わった人が行った部分が、分けることができない場合には、共有著作権となる可能性があります。
そのような場合には、その作成過程に関与したプログラマの特定が必要です。
開発者と会社の関係
開発者が特定できた場合でも、職務著作が成立する場合には、使用者(企業)に原始的に著作権が帰属します。
職務著作とは、会社の業務として、従業員が作成したものは、会社に著作権が帰属するというものです。
以下の場合には、職務著作の成立が認められやすいといえます。
- 当該開発者と所属する会社の間に雇用関係がある
- その指揮監督下において開発作業が行われる
会社の従業員が業務上開発したプログラムについて職務著作が否定されるケースは稀です。
しかし、システム開発においては、フリーランスのプログラマに作業を再委託したりすることもあります。
このような場合に、職務著作の規定によって、原始的に発注者である会社に権利が帰属するといえるかどうかは、当該プログラマと委託したベンダとの指揮命令関係の程度に依存します。
ケースバイケースになるため、職務著作が成立し得る状況であったとしても、事前に権利の帰属、移転について明示的に合意しておくことが重要です。
著作権譲渡の合意があるか
ペンダからユーザへの権利譲渡については、権利を譲り受けたと主張する者が移転の合意について立証責任を負います。
プログラムの開発委託契約に基づいて開発されたプログラムの著作権につき、受託者に発生した著作権を委託者に譲渡するのか、受託者に留保するのかは、契約当事者間の合意により自由に定めることのできる事項です。
このような紛争を未然に回避するためには、システム開発委託の際に、著作権の帰属・譲渡あるいは、ペンダからの利用許諾の範囲、条件について、明示的に合意しておくことが重要です。
著作権者の特定が必要
以上のように、まずは、誰に著作権が帰属しているのか、そして移っているのかを特定することが必要です。
ここに権利があるだろうと勝手に判断して、後から、権利者が現れるなどの事態が生じないようにしましょう!
LINEで問い合わせをする&10大特典を受け取る
LINEの友達追加で、企業に必要な契約書雛形、