適格消費者団体から「通知書」が届いたときの企業としての対処方法【弁護士の解説】【2023年3月加筆】
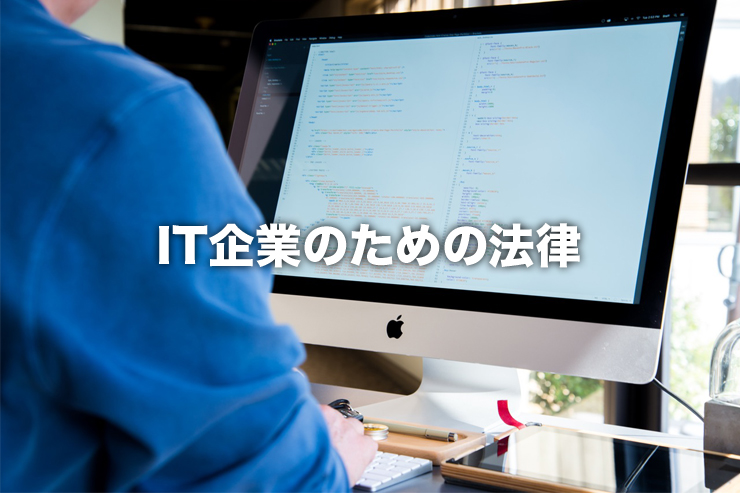
適格消費者団体から通知が来た
BtoCサービスをしていると、適格消費者団体というところから通知書が届くことがあります。
このような場合、事業者としては、どのような対応をすればよいのでしょうか?
適格消費者団体とは
平成19年6月から消費者団体訴訟制度がスタートし、事業者が行う、不当な契約条項の使用、不当な勧誘行為、不当な広告表示に対する差止請求を行う権利を、一定の要件を満たす消費者団体に認めました。
この団体を「適格消費者団体」といいます。
差止請求の対象となるのは、事業者の以下のような行為です。
消費者契約法
- 不当な勧誘行為(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害)
- 不当な契約条項
- 事業者の損害賠償の責任を免除する条項
- 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等
- 消費者の利益を一方的に害する条項
景品表示法
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示に該当する広告・表示
特定商取引法
- 不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑、断定的判断の提供といった不当な勧誘行為
- 著しく事実と相違する表示又は誇大広告
- クーリング・オフを無効とするような特約又は契約の解除等に伴う損害賠償の制限額を超える額の特約等を含む契約の締結
事業者が、以上のような行為を行った場合、また利用規約や契約書に記載があり、契約行為を行った場合には、適格消費者団体から差止訴訟がされる可能性があるのです。
適格消費者団体の通知書に対する適切な対応方法
最初から、事業者に対して、適格消費者団体から、訴訟がされるということはありません。
最初は、事業者宛に、通知書が届きます。内容は、事業者が上記の差押請求の対象となっている行為をしているので、是正するようにといった内容です。
この通知書が届いたら、まずは、法律上、差押請求の対象行為を行っているのか、判断する必要があります。
消費者団体訴訟制度差止請求事例集によれば、平成19年6月から平成25年7月までの間に、提起された差止請求訴訟のうち、訴訟が終了した17件のうち、原告勝訴5件、和解9件、原告敗訴3件という結果になっています。
適格消費者団体から、通知が来たからといって、法律上、全ての場合に、差止請求が認められるわけではありません。まずは、事業者として、法律的な判断をする必要があります。
そして、通知書にはきちっと対応する必要があります。適格消費者団体は、消費者を代表して、訴訟をする権利があります。
そのため、通知書に対応しないと、訴訟をする可能性が高いです。訴訟をされると、裁判手続なので、非常に面倒な手続きが生じます。
また、訴訟されると、公の手続きになるので、報道されるなどして、会社の評価リスクも生じることになります。
もちろん、法律的に問題ないと判断すれば、その旨を回答する。法律的に問題あれば、きちんと認めた上で、今後の対応策を回答する必要があるのです。
DeNA社「モバゲー」の利用規約の差止訴訟
最近の事例としては、DeNA社「モバゲー」の利用規約が、消費者契約法に違反するとして、NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」がモバゲー利用規約の使用差止を求める訴訟を提起しました。
モバゲー利用規約「違法」 弁護士らDeNAを提訴(産経ニュース)
「埼玉消費者被害をなくす会」は、弁護士が中心となって運営している団体で、適格消費者団体です。
これは、DeNA社「モバゲー」の利用規約で、「当社は一切の責任を負いません。」とした条項の使用の差止を求めたものです。
DeNA側は、消費者契約法に違反しないと争っているようですので、結論は分かりませんが、事業者としては、利用規約の条項については、消費者契約法に違反しないように、規定しておく必要があります。


















