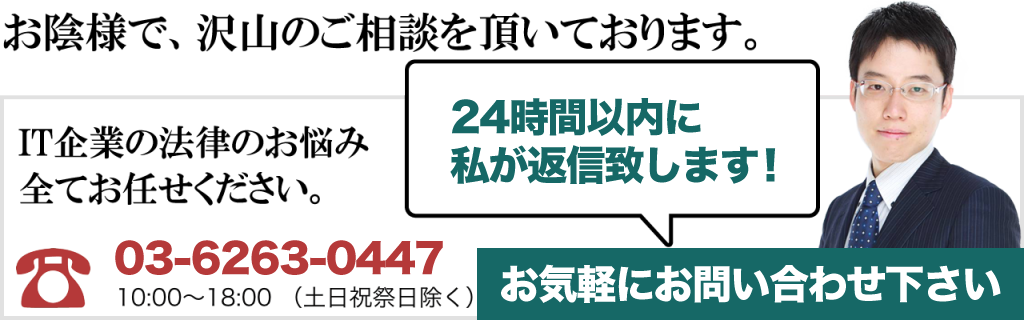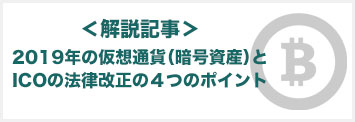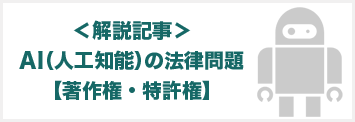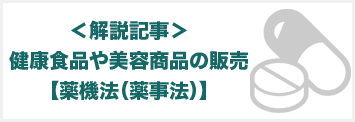シェアオフィスサービスの法律的注意点

シェアオフィスとは
シェアオフィスとは、その名のとおり、事業者がオフィス用途で提供する空間・設備等を、複数の企業・個人事業主等でシェアして活用するビジネスオフィスの形態のことであり、貸机業とも称されます。
月額料金を定額で設けて、利用者は、契約期間中であれば提供されるワークスペースを他の利用者との共有の下、使用することができます。このようにシェアオフィス事業は、サブスクリプションサービスの事業形態によることが通常です。
従来型の会社形態と比較した場合におけるシェアオフィスのメリットとして、会社のランニングコストやオフィス費用を低コストで抑えることができる点が挙げられます。
また、ワークスペースの利用形態にもよりますが、中には法人登記が可能なシェアオフィスも存在します。
シェアオフィス事業の法律的留意点
法的性質
従来型の会社形態においては、賃貸物件をオフィス用途で使用する場合、物件所有者との間で「建物賃貸借契約」を締結することが一般的です。
これに対してシェアオフィスを利用する場合、シェアオフィス事業者と利用者との間で締結される契約は、「施設利用契約」や「サービスオフィス契約」などの名称が付されることが通常です。
確かに、通常の建物賃貸借契約と比べて、シェアオフィスは物件の一部スペースの使用・共用を許諾する性質であるため、伝統的な賃貸借契約になじまない部分もあります。
しかしながら、このことから当然に建物の賃貸借と扱われないとは限りません。特に建物賃貸借契約として扱われる場合には、借地借家法の適用があるため、契約の法定更新事由の存在などに気を付ける必要があります。
裁判例
上記の点は、事業を検討するに当たり注意しておくべき事項です。
以下、シェアオフィスについて建物賃貸借契約該当性が否定された事案と肯定された事案の2つの裁判例を紹介します。
否定裁判例
本件事案において、建物賃貸借か否かが争われたのは、転貸人である原告が、転借人である被告に対して行った転貸借契約の解約申入れの効力が争点とされたためです。
仮に本件転貸借契約が建物賃貸借として扱われるとすれば、原告の解約申入れに借地借家法28条の適用があり、建物の借主保護のため、解約申し入れに「正当事由」の存在が必要になります。すなわち、通常の賃貸借のように、単に解約を申し入れただけでは契約を解約するには足りないことになります。
本判決においては、結果として建物賃貸借該当性は否定されました。この判断において重視された要素は、「転貸部分の空間に他の事業者も原告から転貸を受けていたものであり、かつ、転貸目的物の構造・利用状況から、各転借人の転貸スペースにつき境界線が明確に区画されていなかった」点にあると解されます。
このため、本件転貸部分の空間につき、被告が独占的排他的支配を有する部分がないと判断されたため、建物賃貸借該当性が否定されました。
肯定裁判例
次に、建物賃貸借該当性が肯定された裁判例を紹介します。本件事案で建物賃貸借該当性が争われたのは、借地借家法26条の適用があるか否かが、賃貸人である被告の行った契約の更新拒絶の効力を左右するためです。
すなわち、建物賃貸借に当たるとして借地借家法の適用を受ける場合、契約の更新拒絶の通知は契約期間満了の1年から6か月前までの間に行う必要があります。建物賃借人保護のため、更新拒絶を行う時期は早すぎても遅すぎても認められないということになります。
本判決は、当該契約が建物賃貸借契約の法的性格を有することを認めました。これは、前述の否定裁判例の事案と異なり、賃貸部分が狭小ではあるものの、四方を天井まで隙間のない障壁で囲まれ、また、共用部分との間は鍵付きのドアによって区画されていたことにより、当該部分について賃借人の「独占的排他的支配」性が認められたことによります。
本判決は、上記に加えて、契約内容についても判断しています。すなわち、一般的なシェアオフィスがサービスとして提供しているインターネット回線や備品の使用、また、オフィス事務関連のサービスは建物賃貸借契約とは別個の契約か、若しくは付帯的なサービスに過ぎないものとして、建物賃貸借契約の性格に影響するものではないと判断しました。
当該シェアオフィスが借地借家法の適用を受けるか否か
上記2つの裁判例にみられるように、あるシェアオフィスサービスが建物賃貸借契約として扱われ借地借家法の適用を受けるか否かは、賃貸目的物に係る利用者の独占的排他支配性の有無や目的物の構造、利用条件等によって、異なってくることに注意が必要です。
借地借家法は強行法規であるため、たとえ契約内容に同法の適用除外条項を盛り込んでも、当該条項は無効となります。
既述のとおり、シェアオフィスサービスは、契約当事者双方にとって、建物賃貸借契約として扱われるか否かが重要な関心事となることが想定されます。事後的トラブルを避けるために、開業前の段階で入念に事業計画を立てておくことが重要となります。