【仮想通貨法の内閣府令・金融庁ガイドライン】事業者が利用者に対する情報提供措置とは?
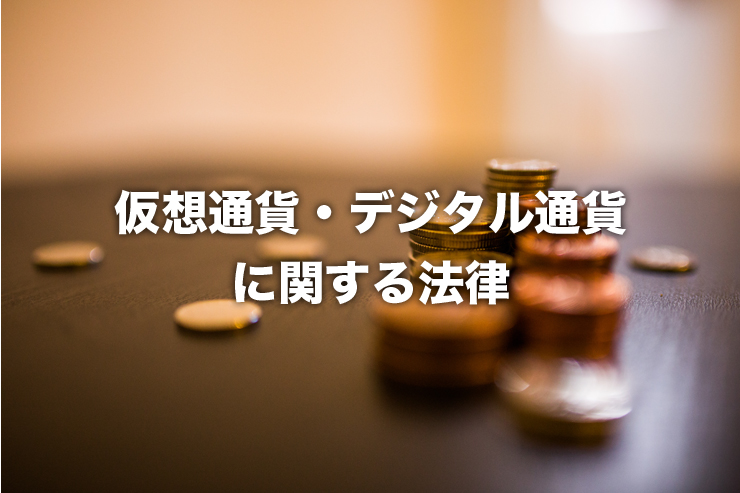
仮想通貨事業者は利用者に対して「情報提供する」必要がある
仮想通貨事業者は、利用者保護の一環として、利用者に対する説明・情報提供をする必要があります。
そこで、今回は、仮想通貨事業者は、利用者に対して、どのような情報を提供する必要があるのかを見ていきたいと思います。
内閣府令では
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは 、あらかじめ当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない(第17条)
内閣府令では上記のようにされています。そのため事業者は、以下の情報を提供する必要があります(一部重要な部分の抜粋です。)
- 当該取引の内容
- 取り扱う仮想通貨の概要
- 取り扱う仮想通貨の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
- 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間
- 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
- その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
金融庁ガイドラインでは
これを受けてガイドラインでは、説明の方法として次のようになっています。
インターネットを通じた取引の場合には、利用者がその操作するパソコンの画面上に表示される説明事項を読み、 その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法
対面取引の場合には、書面交付や口頭による説明を行った上で当該事実を記録しておく方法がそれぞれ考えられる。
よって、自社の形態に合わせた説明の方法を選ぶ必要があります。
具体的な記載内容とは
利用者対する情報に記載するものとしては、利用者の知識、経験等を勘案して、取引形態に応じて適切に説明を行っているかが大事とされています。
つまり、仮想通貨に知識のない利用者を相手にするのであれば、それに合わせた説明をしなさいということです。
- レバレッジ取引を提供する場合、利用者は提供されるレバレッジ倍率に比例して高額の損失を被るリスクを負うこととなるため、例えば、当該レバレッジ取引によるリスクの大きさ等も適切に説明することが考えられる
- 利用者が当該仮想通貨交換業者以外の者に対しても手数料、報酬若しくは費用(以 下「手数料等」という。)を支払う必要がある場合には、当該委託先に対するものも含 めて手数料等の総額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を説明しているか
- 手数料等の実額ではなく上限額や計算方法のみを説明する場合には、利用者が実際に支払うこととなる手数料等の総額の見込み額又は計算例を併せて説明することとしているか
- 仮想通貨交換業に係る取引に関する金銭及び仮想通貨の預託の方法
- 当該取引に関する金銭及び仮想通貨の状況を確認する方法
- 利用者が口座開設契約等を締 結するか否かの判断を行うに際して、参考となる事項を必要に応じて説明しているか
(例)暗証番号の設定その他のセキュリティに関する事項
(例)口座開設契約等により、利用者ごとに仮想通貨交換業者が受け入れられる金額に上限がある場合には、当該上限金額
以上のように、利用者が損をする恐れのある事項については、重点的に情報提供する必要があるのです。
利用者に対して分かりやすい説明を
仮想通貨法では、金融庁が監督官庁になって、事業者を監督していきます。
仮想通貨法では、利用者保護を鮮明に打ち出している以上、事業者に対して分かりやすい説明をしないと、金融庁から指導などがあるかもしれません。
事業者として、どの事項について、どのような記載をするのかを改めて一度確認しておきましょう!


















