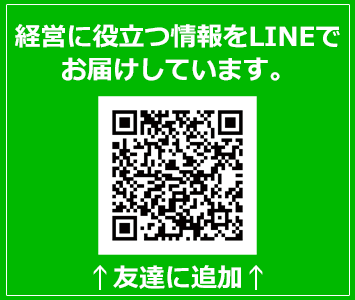EdTech(エドテック)で注意すべき法律をITに強い弁護士が解説【2022年3月加筆】

EdTech(エドテック)の普及
EdTech(エドテック)とは、教育(Education)と技術(Technology)を組みわせた言葉で、AIやITを活用した教育ビジネス領域を指します。
利用者が拡大している「スタディサプリ」や先生と生徒のオンラインラーニングプラットフォームであるQuipper オンライン家庭教師サービスである「manabo」などがあります。
このようなEdTech(エドテック)を運営する教育系ベンチャーにとって、気を付けるべき法律とは、どういったことでしょうか。
特定商取引法の規制
特定商取引法では、学習塾や家庭教師については「特定継続的役務提供」という規制がかかります。
具体的には、2か月以上で、総額5万円を超えるサービスについては対象になりますので、注意が必要です。
この「特定継続的役務提供」の対象になると、以下のような規制がかけられます。
概要書面と契約書面の交付
「特定継続的役務提供」している事業者は、契約締結前には「概要書面」を契約締結後には「契約書面」を添付する必要があります。
概要書面の内容
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
契約書面の内容
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
クーリングオフの対象に
「特定継続的役務提供」については、クーリングオフの対象になります。
上記の契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフをすることができます。契約書面を交付していないと、いつまでもクーリングオフができてしまいますので、注意してください。
オンラインでのプログラミング指導は特定継続的役務提供?
オンラインでのプログラミング指導は「特定継続的役務提供」に当たるのでしょうか。
消費者庁及び経済産業省で検討を行った結果、パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り「特定継続的役務」に該当しない旨の回答ができています。
インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます
未成年者ユーザーの問題
EdTech(エドテック)サービスの場合、ユーザが、未成年者という場合が多いかと思います。
未成年者の場合「保護者の同意がない場合には、未成年者はその取引をいつでも取り消すことができる」というのが民法上の原則です。
つまり有料サービスを未成年者が保護者の同意なく申し込んだ後、取引を取り消されてしまうと、当初から契約がなかったことになり、事業者は、未成年者ユーザーが払い込んだ料金を返金しなければならないという事態になってしまいます。
対策としては、以下のようなことが考えられます。
- サービスのUI上に、親権者の同意が必要である旨の告知をする
- 利用規約で、サービス利用には、親権者の同意が必要である旨の記載する
- 年齢認証画面を設ける
- 月額定額制を導入する
アプリにおける利用規約のチェックポイント~ユーザーが未成年者の場合を考える
民法5条3項では、親が目的を定めて、処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。とされています。
未成年者が支払う金額で、比較的低額で一定額であれば「処分を許した財産」とされる可能性があり、未成年者が取り消すことができなくなる可能性があります。
AIを使ったEdTechサービスの注意点
最新のEdTechは、AIを活用したものも、増えています。人工知能型タブレット教材「Qubena(キュビナ)」などは、その最たる例です。
AI技術を活用したEdTechサービスの法律的な注意点としては、以下の通りです。
AIに与える学習用データの問題
例えば、数学の問題を学習をさせるために、多くの資料・文献を学習用データとして読み込ませる必要があります。この既存の資料・文献を学習用データとして読み込ませる行為が、著作権に違反しないのかが問題になります。
この点については、解説記事「AI(人工知能)の法律問題【著作権・特許権】」をご参照ください。
AIが作成した教育プログラムの権利は
AIが作成した教育プログラムについては、著作権等が認められるのも問題になります。この点については、最終的に人が監修していたのであれば、そのAI教育プログラムには、著作権が認められる可能性があります。
しかし、AIが人の手を離れて、教育プログラムを作成した場合には、著作権などの権利が問題になります。
この点については、上記と同じように、AI(人工知能)の法律問題【著作権・特許権】で解説していますので、ご参照ください。
EdTech(エドテック)サービスは、法律に注意して設計を
以上のように、EdTech(エドテック)サービスは、複数の法律を検討する必要があります。後から、法律で行き詰ることがないように、しっかりサービスを設計しておきましょう。