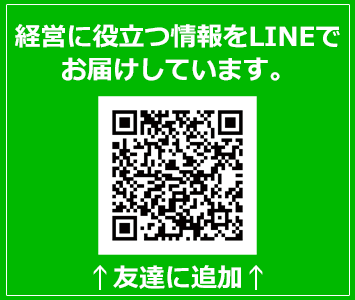著作物の権利者が分からないときは「著作物の利用に関する裁定制度」で対応しよう

著作物を利用したい…でも、誰かわからない
許諾を受けて著作物を利用したいけど、誰が権利者か分からない…そんなときに遭遇します。
そんなときに、どうすればよいのでしょうか。
一つの手段としては、無断で使っちゃうというのがあります。しかし、後から権利者が現れて、著作権侵害と言われると、非常に面倒です。
特に、ビジネスで使う場合で、それなりに資本も投下している場合には、サービス停止になってしまったら、シャレになりません。
そんなときには、著作物の利用に関する裁定制度があります。
著作物の利用に関する裁定制度とは
このような場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより,適法に利用することができる制度が著作権法上設けられています。
裁定の申請を行うために必要なこと
裁定制度は、権利者が不明である場合に、許諾を得ずに利用することができる制度であるため、権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の「相当な努力」を行うことが必要とされています。
そして、「相当な努力」をしても、権利者と連絡を取ることができない場合に裁定制度が利用可能とされています。
「相当な努力」とは
- 権利者の住所氏名等の著作権者と連絡するために必要な情報(=「権利者情報」)を取得するための所定の措置をとり
- (1)により取得した権利者情報及び保有するすべての権利者情報に基づき権利者と連絡するための措置をとったにもかかわらず、権利者と連絡することができなかった場合とされている
(1)の所定の措置とは、以下のいずれかの措置を取ることとされています。
- 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること
- 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により,公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること
(1)文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧とは、文化庁から出されているものやインターネット上の検索などを指します。
裁定の決定前における利用
文化庁に裁定申請を行うと、裁定の決定前であっても、文化庁長官の定める担保金を供託すれば,著作者が著作物の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除いて、裁定の決定前であっても、著作物等の利用を開始することができます。
ただし、法定の要件を満たさなかった等の理由で裁定を受けられなかった場合(「裁定をしない処分」を受けた場合)には、その時点で著作物等の利用を中止しなければなりません。
裁定制度の利用方法
裁定制度は、文化庁長官に裁定の申請をして進めるものであるため、文化庁において制度利用のための詳細な手引き(文化庁のウェブサイトから入手可)を用意しています。
裁定の手引き
また、裁定制度を利用する場合には、事前に文化庁に相談することが推奨されています。
裁定の処分と裁定に基づく著作物等の利用
法定の要件を満たす場合には、文化庁長官は、裁定の処分を行うことになります。
申請者が申請書等を文化庁に提出してから裁定の可否の決定を受けるまでの標準処理期間は約2か月が想定されています。
文化庁長官は,裁定の処分を行う場合には、文化審議会に諮問して補償金の額を決定し、裁定の可否を通知する書面において併せて通知します。
補償金の額は、通常の使用料の額に相当する額とされており、著作物等の種類や利用方法,利用期間等によって異なります。
このため、文化庁長官は、申請のあった著作物等を利用する場合の一般的な利用料金等を参考に補償金額を決定します。
裁定を受けた場合、申請者は、文化庁長官が定めた補償金の額を供託所に供託しなければななりません。
裁定決定前の利用を行っていた場合で、裁定後の補償金の額の方が上回る場合には、その差額を迫加して供託しなければなりません。
裁定後の補償金の額の方が下回る場合には、その差額を取り戻すことができます。
この供託が完了したことをもって、著作物等を利用することができます。
著作権の裁定制度を利用して、コンテンツの利用を
以上のように、裁定制度を利用することにより、権利者不明のコンテンツでも、公式に利用することができます。
事業者としては、後から権利侵害の心配がないことになるので、活用を検討してみましょう!