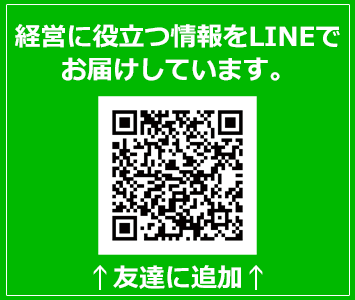セキュリティトークンやユーティリティトークンなどのICO法律的規制の今後とは
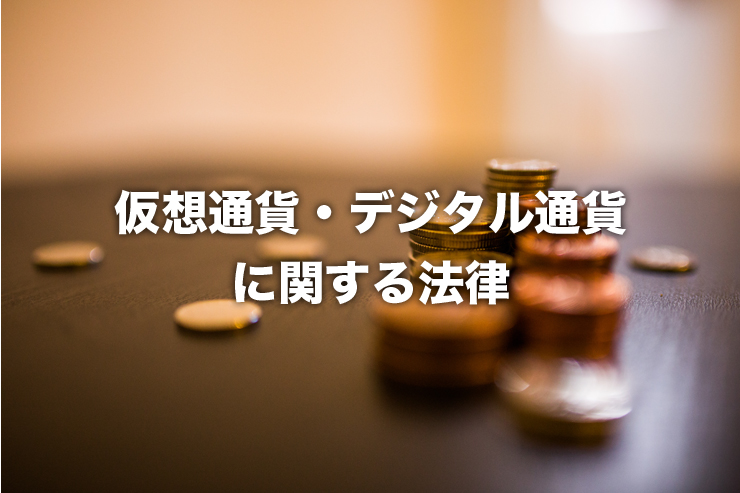
仮想通貨交換業等に関する研究会での「ICO規制」の今後
先日、金融庁で、「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第10回)が開催されました。
今回、ICO規制に関するテーマが中心的なテーマだったのですが、今後のICO規制の方向性について、具体的に論じられています。
今回は「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第10回)で論じられた、ICOの法律的規制について、解説していきます。
セキュリティトークンやユーティリティトークン規制の明確化
ICO規制を論じるにあたり、金融庁は、トークンの性質に着目しました。
そして、トークンに「投資性」があるかどうかで、法規制の枠組みを変えることを予定しています。
トークンを持っている投資家に対して、配当がある場合(セキュリティトークン)
このようなトークン、いわゆるセキュリティトークンについては「投資性がある」として、金融商品取引法で規制する予定であることが規定されています。
決済手段などの配当ないトークン(ユーリティトークン)
投資家に配当がなく、決済手段などで使用されるユーティリティトークンについては「投資性がない」として、仮想通貨法(改正資金決済法)で、規制していくとされています。
ただし、ユーティリティトークンであっても、仮想通貨取引所に「上場」をした場合には、「投資性」があるのかは、明確にはされていません。
トークンが仮想通貨取引所に「上場」があれば、「投資性がある」とされてしまうと、金融商品取引法の適用がある可能性があります。
後述するように、金融商品取引法の規制があると、非常に面倒な制約が多数かかることになりますので、金融庁の今後の動きには、注意が必要です。
セキュリティトークンへの法律的規制
それでは、セキュリティトークンについては、具体的にどのような規制が課せられる可能性があるのでしょうか。
上記のように、金融庁は、セキュリティトークンについては、金融商品取引法で、規制していく方針ということでした。金商法の適用があると、以下のような規制がかかることになります。
金融庁への登録義務
金商法で規制されるとなると、セキュリティトークンの発行事業者は、金融庁への登録が必要になります。
この金融庁への登録ですが、非常にハードルが高く、スタートアップやベンチャー企業には、相当な負担がかかります。
広告規制
広告には業者の商号・名称、金融商品取引業者である旨、登録番号及び政令で定める事項を表示しなければなりません。
表示すべき事項を表示せず、または虚偽の表示をした者に対しては、6月以下の懲役、50万円以下の罰金が課せられます。また、誇大広告の禁止など、広告する際の文言も規制されています。
契約締結前、締結時などの書面交付義務
金商法の適用がある事業者は、契約を締結する前と契約締結した後に、書面交付義務があります。
これは、法令上、記載するべき事項が決まっていますので、注意が必要です。
説明義務
事業者は、取引の内容について、十分に説明する必要があります。
金融庁への報告義務
以上のほか、様々な行為規制を受けることになりますが、一番負担なのは、金融庁に対する報告義務です。
金融庁への登録をするということは、金融庁の監督下に入るということなので、金融庁からの指導には、従う必要があります。
STOについては、合法的に行える方法として、注目されていますが、上記のように法律を遵守することが大前提になります。特に、セキュリティトークンが、金融商品取引法の対象になれば、法律の遵守自体が非常にハードルが高くなりますので、注意が必要です。
ICOに代わる方法であるSTOとIEOの特徴と法律について【解説】
ユーティリティトークンの法律的規制
上記のように、ユーティリティトークンについては、金商法上の対象ではなく、仮想通貨法の対象となるとされています。
今回の研究会では、ユーティリティトークンについて、具体的にどのような規制になるとは言及されていませんが、仮想通貨法の対象になるということは、トークン発行事業者に対しては、仮想通貨交換業の登録を義務つけるといった法改正がされる可能性があります。
ICOを実施する際の法律的規制
以上の他に、今回の研究会では、ICOを実施する際にも、規制が課せられるべきではないかという意見が出されました。具体的には、以下の通りです。
勧誘できる投資家の制限
ICOについて、投資家を保護する観点から、一般の投資家に対して、広くトークンを勧誘・販売するのはどうなのかという意見が出されています。
特に、セキュリティトークンなどの「投資性を有する」トークンの販売については、適格投資家のみが扱えるようにするという規制案が出ています。
特に、上場していないトークンのうち「投資性のある」トークンについては、一般の投資家に広く勧誘・販売の禁止という規制がされる可能性があるのです。
第三者機関による審査
IPOの資金調達については、事前に審査を受けることになっており、ある程度の安全性が確保されています。一方、ICOについては、現状、そういった事前の審査は、何もない状態です。
このような現状を踏まえ、ICOを実施する場合にも、事前の審査を経る必要があるのではという議論がされました。
もっとも、ICOについても、IPOと同様に詐欺的な行為や曖昧な権利などの発行の防止、事業の実現可能性の確認などの必要性は存在します。そのため、トークンの発行者とは別の第三者が発行者の事業や財務状況を審査するような仕組みを作ることを検討する必要があります。
トークンを取引できる場所の制限
研究会では、株式については、証券取引所などの一定の場所でのみ購入することができることと対比して、ICOについては、そういった規制がないことを問題視しました。
そこで、ICOトークンについて、一定の取引所のみで売買できるようにするという規制案も出ています。
トークンのインサイダー規制
株式では、インサイダー取引や相場操縦などの厳しい規制があります。
例えば、上場会社の関係者やある情報を知った人が、その会社の株価に影響を与える重要な事実を知りながら、その事実の公表前に、会社の株式などを売買するのは禁止です。
一方、仮想通貨やトークンの売買に関しては、そのような規制は存在していません。金融庁としては、仮想通貨・トークンについても、同様の規制をかけることを念頭におき、規制する方向で議論しています。
ただし、トークンの場合、どういう情報が、価格に影響のある情報が明確ではありません。その点で、今後、どのような立法がされるのかは、注目されるところです。
IEO(Initial Exchange Offering)の規制について
今回ですが、IEOの規制についても、言及されています。IEOとは、トークンの販売や配布などを、既存の仮想通貨交換業者に委託して行う方法のことです。
ICOに代わる方法であるSTOとIEOの特徴と法律について【解説】
実際に、トークンの販売等を行うのは、仮想通貨事業者なので、発行事業者は、仮想通貨交換業の登録は不要です。
今回、問題になったのは、委託を受けた仮想通貨交換業者です。
委託を受けた仮想通貨交換業者は、以下のような情報を、投資家に開示すべきではないかという議論がされました。
- 発行者に関する情報、発行者が仮想通貨の保有者に対して負う債務の有無・内容、発行価格の算定根拠
- ICOの場合には、「1」に加え、発行者が作成した事業計画書、事業の実現可能性、事業の進捗
ICOの法制化は、来年以降に
上記のICO法規制ですが、来年の通常国会で、法制化を目指すとしています。
「ICO」、個人投資家の勧誘制限=仮想通貨規制、金商法改正へ-金融庁
成立時期、施行時期などは不明ですが、事業者としては、今後の法律の動きに注目する必要があります。