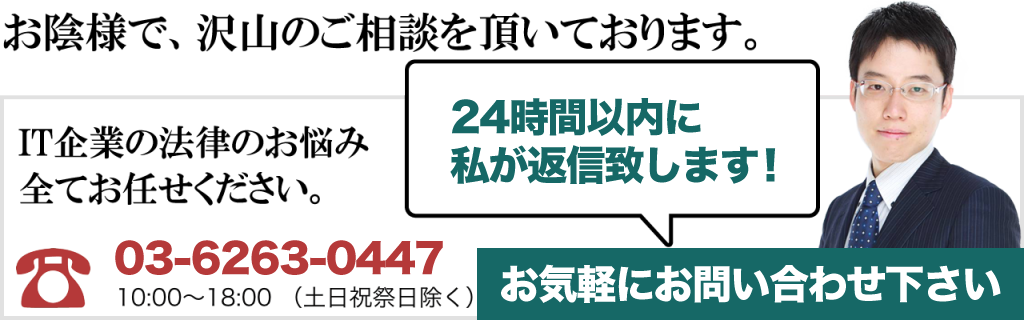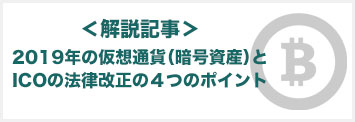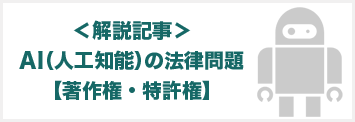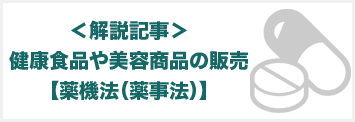システム開発で機能の変更追加があった場合に明確な約束がなくても報酬は支払ってもらえるか?

明確な金額の合意がない機能追加の場合に代金を請求できる?
システム開発の現場では、プロジェクトの開始時に想定していなかった機能の追加開発や仕様変更(以下「追加作業」という。)が頻繁に発生します。
しかし、この追加・変更があまりにも頻繁に発生するので、逐一その変更分について、これぐらいの工数で、単価で金額いくらといった明確な合意がなされていないことが、ほとんどです。
ベンダ側も、発注者であるユーザ企業との関係を考え、変更・追加作業に対する報酬を請求しないという対応を取ることも多いのが実情ではないでしょうか。
紛争に発展するのは、ベンダ企業とユーザ企業の関係がこじれ、当初約束していた報酬すら支払ってもらえなくなったときです。この時に、ベンダ企業は、ユーザ企業との関係がなくなっても構わないと考え、今までの請求できる分を全て請求するという形で、訴訟提起などに踏みきることがあります。
この場合に、先ほどの追加・変更分の報酬も上乗せで請求したいと思う場合には、追加・変更分の報酬について、合意がない場合でも、ユーザ企業に請求できるのでしょうか?
追加・変更分は「相当な報酬」が請求可能
通常は、「この仕様を、この金額で完成させます」という合意(契約)がないと、ベンダ企業は、ユーザ企業に請求できません。
しかし、このような場合でも、請求できる法律があります。それが、商法512条です。
商法512条は、以下のとおり規定しています。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
ここで問題になるのは「相当な報酬」とは、どの程度の請求ができるかということです。過去の裁判例では、以下のような算出がされています。
- 「1人日当たりの作業可能ステップ数」から、追加開発部分が何人日の作業であるのかを算出(平成11年大阪地裁判決)
- システムのプログラム1本当たりの単価に追加開発したプログラム数を乗じて算出(平成14年東京地裁判決)
- 3か月間における作業の対価を基準として、追加開発に要した期間から算出(平成18年東京地裁判決)
以上のように、裁判所としては、システム開発の報酬の大部分が、エンジニアの人件費であり、その人件費は、開発するシステムの分量によって増加するという考え方を取っています。
つまり、ベンダ企業の作業量に応じた報酬を認めています。これは、実作業に対する報酬を請求できるという意味で、ベンダ側に有利な裁判例といえます。
追加・変更作業が発生する場合のルールを守っていることが必要
上記のように、明確な合意がなくても、追加・変更分に対して「相当な報酬」が請求できることになりそうです。
しかしこれは、あくまで、追加・変更分が発生する前の当初の段階で、追加・変更が発生取り決めが、しっかり規定している場合の話です。
例えば、ベンダ側が、変更追加作業が別途有償であることが、文書(メール)などで一切示されていない場合、契約書などにおいて、変更・追加作業が発生する場合の取り決めがあるにも関わらず、ベンダ企業がそれを行っていない場合には、上記の「相当な報酬」が認められない可能性もあります。
特に、当初の契約で、ベンダ企業が変更・追加作業がする場合には、ユーザ企業からの作業依頼書やベンダ企業側が見積書を発行する必要がある場合には、これに沿った対応しなければなりません。
ベンダ企業としては、「やるべきことはやった」といえる体制を取っておくことが大事なのです。