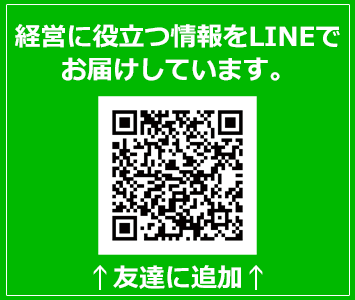SES契約に関する法律と労働局の調査ポイントと対策【2022年1月加筆】
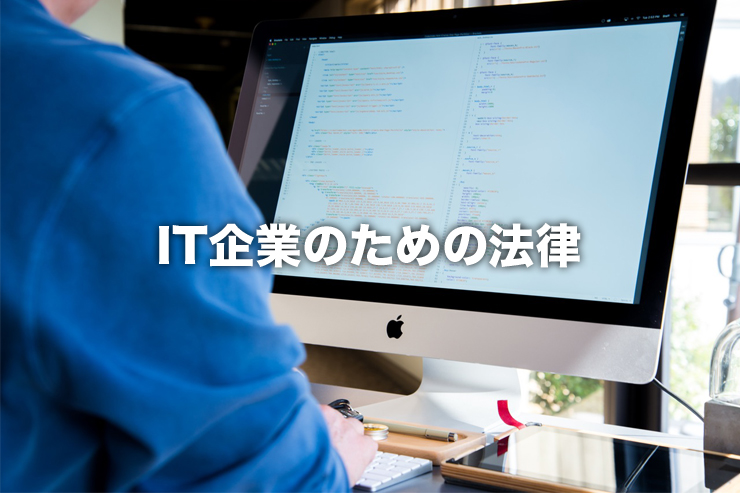
SES契約についての法律
SES契約については、IT業界では多く行われている形態です。
SES契約については、労働者派遣法との関係で、問題になるケースがあります。しっかりと法律のポイントを理解していないと、法律違反になる可能性があります。
SES契約の法律については、下記で解説していますので、参考にしてください。
SESに関する労働局の調査
上記のように、現在、システム開発系の企業で、多く取られている形態であるSES契約ですが、実態の運用として、法律違反の可能性があるケースも多いのが実情です。
労働局としても、違法に運用されているSESの実態があることは把握していて、労働局の調査が行われています。
特に、今年の9月29日に特定派遣が廃止されますが、そのタイムミングもあってか、今年に入って、労働局の調査が多くなっています。
そこで、労働局の調査というのが、どのようなものなのか、実際の事例をもとに、解説していきます。
労働局からの通知
まずは、会社に、電話か郵送で、労働局から連絡があります。そこには、「労働者派遣事業等にかかる訪問調査の実施について」といった書面が同封されています。
その書面の中には、以下のようなことが記載されています。
- 訪問予定日時
- 訪問予定職員
- 調査対象の契約
- 調査当日にご用意いただく書類
「調査当日にご用意いただく書類」として、以下のようなものが記載されています。
- 契約書
- 料金にかかる書類(見積書、請求書、支払書)
- 作業指示書、発注書
- 座席表、作業スケジュール表
調査当日までに、指定された資料をそろえる必要があります。
もし、都合が悪いや当日までの準備期間が少ない場合には、連絡してその旨を伝えれば、期日を延ばしてくれます。
労働局からの調査期日
調査期日当日は、労働局の調査官が、会社を訪れて、ヒアリングすることになります。ヒアリングする事項としては、ケースバイケースなのですが、よく聞かれる質問としては、以下の通りです。
- SESで派遣された従業員に対して、どのように指揮がされていたのか
- 日常の作業指示は、どのような系統で行われるのか
- 派遣されている従業員の勤怠管理はどうなっているのか
この調査期日は、非常に重要で、この対応で、後に述べる処分が決まりますので、十分注意してください。
労働局からの処分
上記の調査期日の後、問題があれば、労働局から処分されます。処分の内容については、以下の通りです。
口頭での注意・指導
違反の事実があったが、ごく軽微であった場合や現在は改善されている場合などは、口頭での注意・指導で終わる場合があります。
労働局からの是正報告・是正指導
違反の内容があり、是正の必要がある場合は、労働局から、是正指導がされます。
是正指導とは文書で、以下の2点が記載されたものです。
- 違反事項
- 是正のための措置
そして、是正のための措置をしたことの報告が求められるのですが、それが是正報告です。
是正報告については、以下のような記載をする必要があります。
(記載例)
●●株式会社との業務委託契約に基づき、以下の通り是正しました。
- 契約者間で、現場責任者を書面にて定め、連絡調整を行うこととし、労働者への指揮命令は、受託者の現場責任者より行う体制としました
- 作業場所を別紙図面の通り、発注者と明確に区別しました
そして、上記の是正措置を裏付ける書面(契約書、作業指示書など)を添付書類としてつけます。
この是正指導、是正報告は、労働局内部の処分であり、是正指導されたことが、外部に公表されることはありません。
なので、企業としても、是正指導、是正報告の処分であれば、実際上のダメージはありません。
業務改善命令・業務停止命令
違反の程度が重大である。過去に、是正指導された経験があるなどの悪質性がある場合には、労働局から業務改善命令・業務停止命令が出されることがあります。
この処分で影響が大きいのは、業務改善命令などの行政処分がされたことが、公表されてしまうことです。
派遣禁止業務への労働者派遣を行っていた派遣元事業主に対する行政処分について
今後の取引にも影響しますし、リピュテーションリスクも生じます。企業にとっては、死活問題ともいえるでしょう。
SES契約の適法化のポイント
弊社で相談を受けているSES契約には、法律上グレーな部分で運用されている契約もあります。その契約を適法化したいという相談をよく受けます。
では、労働局の調査対策の観点から、SES契約を適法化するためには、どのような対策をすればよいのでしょうか。詳しい適法化のポイントは、以下を参照してください。
作業指示系統の見直し
上記の通り、労働局の調査において、SES契約で、一番聞かれるのが、作業指示がどのようにされているのかです。
常駐先のクライアント側で、ベンダ側のエンジニアに指示がされていたら、労働者派遣とみなされてしまい、法律上、アウトになります。
対策としては、クライアント側からベンダ側の責任者に作業指示書等で、作業指示を行い、ベンダ側の責任者からベンダ側のエンジニアに作業指示を出すというやり方です。
このときに、注意が必要なのが、作業指示書の内容です。
作業指示書には、業務内容を記載することになりますが、この作業指示書に記載されている業務内容を、具体的に記載する必要があります。
というのは、クライアント側は、直接、ベンダ側のエンジニアに指示できないので、作業指示書には、それをみてエンジニアが作業できるだけの情報が掲載されている必要があります。
具体的には、以下のような項目を記載します。
- プロジェクト名
- 指示者名
- 工程
- 業務内容
特に、業務内容については、できる限り、詳細に記載するようにしてください。
また、作業指示書の業務内容の記載だけでは、記載に限界があると思いますので、それに加えて、作業マニュアルも用意した方がよいです。
実際、労働局の調査でも、作業指示書の内容だけでは、実際の作業ができないとして、指摘されたことがあります。
作業マニュアルは、WBSや仕様書など、システムの全体像が分かるものを用意するとよいでしょう。
労働者管理の資料の整備
労働者の管理については、ベンダ側が行う必要があります。これをクライアント任せにしてしまうと、法律違反になる可能性があります。
よって、労働者の勤怠管理や評価については、ベンダ側で一覧表にするなどの対策が必要になります。
自社の従業員から、労働局に通知された場合の対応
労働局の調査には、以下の二種類があります。
- 労働局の定期調査
- 労働局へ通知がされた(いわゆるタレコミ)
特に、注意が必要なのは、労働局へ通知がされた、いわゆるタレコミ案件です。
タレコミ案件の場合には、労働局へ通知した方が、すでに資料などを労働局に提供していることが多いです。
そこで、以下のようなことは、一番やってはいけません。
- 虚偽の事実をいうこと
- 文書などを改ざんすること
事業者としては、労働局の調査なので、適法に見せたいので、不備がある場合には修正したくなるかもしれません。
しかし、上記のように、タレコミ案件の場合には、労働局も、資料や証拠などをすでに保有している可能性が高いです。
そこで、実際とは食い違う事実を主張したり、ましてや現にある文書を改ざんしたりすると、それが発覚した場合には、一発で、業務改善や業務停止などの行政処分が下る可能性が高いです。
このようなタレコミ案件の場合には、不備があるのであれば、それを認め、今後改善していく姿勢を見せていくことが必要です。
労働局としても、不備があったとしても、適法化に向けての道筋を示せれば、いきなり業務改善のような行政指導が下ることはありません。
事業者としては、タレコミ案件でもあわてずに、対応するようにしましょう。