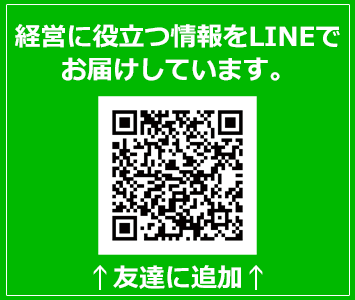YouTubeにカラオケ歌唱動画をアップすることは違法!法律的に何が問題なのか?【2022年12月加筆】

カラオケ動画をYouTubeにアップで公開禁止の判決
自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した東京都内の男性(45)に対し、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡しました。
カラオケ動画投稿ダメ…メーカーの権利侵害判決
この事件は、カラオケ機器のメーカー「第一興商」が、投稿した男性側に削除を求めたというもの。この事件のポイントは、どこにあるのでしょうか?
カラオケ機器のメーカーの権利である「著作者隣接権」とは
そもそも、カラオケの楽曲については、それを作った人(作詞者、作曲者)に著作権があります。
そして、作詞者、作曲者が、自分の楽曲を無断で投稿されたとして、訴えるというならわかります。しかし、今回、訴えたのは、カラオケ機器のメーカー「第一興商」です。
では、カラオケ機器のメーカーは、どのような権利があるのでしょうか。
著作権法の中には「著作者隣接権」というものがあります。
これは、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。
カラオケの楽曲は、オリジナルな楽曲から、カラオケ機器メーカーが独自で作成しているので、カラオケ機器メーカーも、著作者隣接権があり、無断でカラオケ楽曲を使用されると、カラオケ機器メーカーは、著作者隣接権に基づき、権利行使することができるのです。
著作者隣接権を侵害されると、何が請求できる?
著作者隣接権を侵害された場合には、著作権を侵害された場合と同じように、無断で使用された情報・コンテンツなどの差し止め(削除)請求、損害賠償請求をすることができます。
そして、カラオケ機器のメーカー「第一興商」は、動画の削除と今後の当該動画投稿の禁止を求めて裁判を起こしました。
今回、被告となった男性は、訴えられたことによって、問題となっている動画を削除しました。
裁判所は、男性のカラオケ動画の投稿は、第一興商の権利の侵害にあたると認め、男性に対し、今後、当該動画を投稿することを禁止する判決を下しました。
これまでの情報やコンテンツの差し止め(削除)が認められた例はたくさんあるのですが、将来にわたって、当該コンテンツを投稿することを禁止するという判決はあまり例がありません。
コンテンツホルダー側としては、現在の削除と将来的な投稿禁止が認められる可能性が高くなったという意味では、画期的な判決といえるのです。
著作権者の権利意識が高まっている。
第一興商は、これまでも投稿した人たちに、個別に削除を要請していて、その数が年間12万件にのぼっているということです。
近年では、著作権者の権利意識が高まっています。コンテンツホルダー側だけでなく、それを使用する側も、注意するようにしましょう。