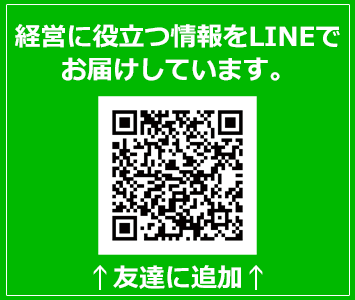判決から読み解く!企業がリンクを貼るときに気をつけるべき著作権とは。【2021年7月加筆】

ウェブサイトでリンク先を表示する方法について
リンクの種類には以下の2種類があります。
- 「通常の方式によるリンク」
→リンク元の画像やテキストをユーザーがクリックすることでリンク先のウェブページを開くようになる方法 - 「インラインリンク」
→リンク元でユーザーが何もクリックをしなくても、リンク先の画像等がリンク元のページに表示される方法
従来のリンク設定の法律
これまでは、ウェブサイトにリンク貼る行為については、著作権のうち、複製権も公衆送信権も貼る行為によって侵害されないという理解でした。
他者コンテンツのリンクを張る行為は法律(著作権法)的にOKですか?
これは、ユーザーが見ているリンク元のページは、リンク先のサーバーが画像等を送信しているからだとされていました。
リンクと著作権について、注目の判決がでた
今まではユーザーは、元のサーバー(リンク先のサーバー)から直接画像等のデータを受信しているため、リンクを貼る行為は著作権侵害にはならないと考えられてきました。
しかし、平成30年4月に「リンクと著作権法の問題」に関して注目すべき判決が出たのです(知財高裁平成30年4月25日判決)。
事案の概要
この判決が出た事案では、以下のようなことがありました。
写真家は自分で撮影した写真の画像データを自分のウェブサイトで公開していた
↓
Aさんが写真家に無断でその写真をウェブサイトからダウンロードし、AさんのTwitterに掲載(転載)
↓
その後、Aさんの当該画像ツイートをBさんがリツイート
↓
写真家は、「自分の撮影した写真の画像が無断で転載されたことは著作権等の侵害である」と主張
↓
写真家はツイッター社に対し、プロバイダ責任制限法に基づき、AさんとBさんの個人情報の開示(発信者情報開示)を請求
ちなみに、Bさんのリツイートの結果、Bさんのタイムライン上に表示される写真家が撮影した写真は、①元々の画像から端部分がトリミングされてしまい、②写真家がサインを下部に表示していたため見切れてしまっていました。
この事案で、Aさんではなく、Bさんが「Aさんの写真家の写真を転載したツイートをリツイートした」という行為が写真家の権利を侵害するかどうか、でした。
判決は
知財高裁は、Bさんは写真家の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害していないと判断しました。
理由は従前の議論と同様に、ユーザーに送信されるデータはBさんがAさんのツイートをリツイートしたとしても、元のサーバー(Aさんが画像ツイートをする際に画像をアップロードしたサーバー)からである、というものでした。
しかしこれとは反対に、写真家の同一性保持権と氏名表示権がBさんのリツイート行為によって侵害されているとの判断がされました。
注目すべき点は、タイムライン上に写真がトリミングされ(同一性保持権侵害)表示されることによって、写真家のサインが見切れてしまっている(氏名表示権侵害)という点です。
写真がトリミングされ写真家のサインが見切れてしまっている結果は、元のサーバーからのデータの送信ではなくBさんのリツイートによる結果だと判断したのです。
企業への影響
「リンクを貼る行為」というのは今までの基本的な考え方を元にすれば、著作権侵害にはならないと考えられてきました。
しかし、上記の判決では、著作者人格権の侵害の可能性がありうるという判断になっています。Twitterでのリツイート行為についての判断ですが、リンクを貼るという行為全般に影響のある内容です。
もちろん、リンクを貼るという行為がすべて著作者人格権の侵害になると言っているわけではありません。
- リンクの貼り方:特にユーザーに送信されるデータはどのサーバーからであるのか
- ユーザーから見た画面にはどのように表示されているのか
等の点がポイントになるのではないかと考えられます。
今回の事案はツイッターでしたが、リンクを貼るという行為というのは他のSNSについても当てはまることです。SNSの場合、これらの点の利用規約や技術的な部分が改訂される度に、結論が変わる可能性は充分あります。
とりあえず今のところは、今まで「リンクを貼る行為は著作権法的に問題ない」と考えていた事業者の方は今回の知財高裁の判決を元にして、リンクを貼る際には「これは権利侵害にならないか?」と一度考えた方が良いでしょう。
まとめ
著作権侵害を起こしてしまった場合、ダメージはサイトの封鎖や損害賠償請求を受けるだけはありません。ユーザーからもコンプライアンスを疑われ信頼を失い、顧客離れにつながる可能性も大いにあります。
自社のウェブサイトが適法に運営されているか、定期的に確認するようにしましょう。