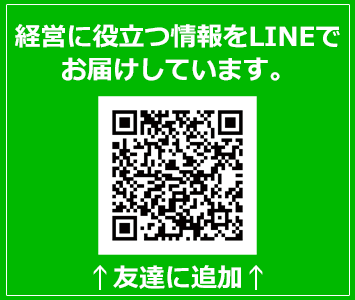AIスピーカーやブロックチェーンを用いた契約の法律とは【「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂版】

経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改定版
2018年7月に「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改正版が公表されました。
この準則は、経済産業省が、インターネットビジネスに関するさまざまな法的問題点における、民法等の関係法律の適用について、解釈を示したものです。
この改定版では、AIスピーカーやブロックチェーンなどの最先端の法律についての解釈基準が付け加えられました。
今回は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改正版について、解説してきます。
AIスピーカーが音声を誤認識した場合
上記の準則では、契約の成立段階で、AIが利用されているケースを取り上げています。
そもそも、契約とは、申込(「これ売ってください」)と承諾(「いいですよ」)があった初めて、成立します。
実際には「申込」がないのに、「申込」があったとAIスピーカーが誤認識した場合では、利用者が何ら「申込」行為を行っていないのだから、そもそも契約が成立していないと考えられます。
AIスピーカーは利用者の自宅に置かれています。そこで、「AIスピーカーの誤動作は利用者の責任」といった見解もが生じかねません。
そこで、準則では、AIスピーカーは、「事業者の支配下にある事業者側の注文受付端末と解釈すべきであ(る)」と明言しました。
よって、AIスピーカーの誤作動については、事業者の責任であるとされたのです。
AIスピーカー事業者としての対策は
これに対し、AIスピーカー提供者がとり得る策として、AIスピーカーが認識した注文内容を利用者に通知し、次のような条項を利用規約に置くことが考えられます。
- 一定期間内に回答がない場合に有効な注文とみなす
- 当該通知に対して、利用者から確認を得られた場合に注文を確定する
注意すべきは、BtoCビジネスの場合で、利用者が消費者のケースでは、消費者契約法10条により、①の条項は無効となる可能性があります。
②の条項は無効となる可能性はないとしています。
AIスピーカーで音声発注をしようとして、うっかり言い間違いをしてしまった場合
利用者が、うっかりしてご発注してしまった場合です。この場合には、錯誤(民法95条)の問題となります。
錯誤の場合には、利用者が、契約の無効を主張することができます。
しかし、利用者は、重過失(重大なうっかり)があれば、意思表示の無効主張ができません。
AIスピーカー事業者の対策
これに対し事業者は、次のような利用規約に置くことが考えられます。
- AIスピーカーが認識した注文内容を利用者に通知し、
- 当該通知に対してユーザーから確認を得られた場合に注文を確定する
上記準則では、そのような確認措置が用意されていれば、利用者に「重過失があると認定される可能性がある」と明言したものです。
ブロックチェーン技術を用いた契約
上記準則では、ブロックチェーン技術を用いて、ブロックチェーン上で管理されるトークンや仮想通貨等の移転を約する契約、例えば、仮想通貨による商品・サービスの購入などがなされた場合、このような契約が有効なのかということが記載されました。
トークン、仮想通貨等は、デジタルな記録であり、民法上の「物」ではありません。
しかし、トークン、仮想通貨等を対価として、現金、物、サービスなどを提供することは、契約当事者が、合意していればOKとして、このような契約も有効とされました。
スマートコントラクトの法的性質
ブロックチェーンに関連する基礎的な事項として、スマートコントラクトの法的性質についても記載されています。
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で動くコード、ソフトウェア一般をいい、契約に基づく債務をブロックチェーンにおいて、自動的に履行することを目的とするものです。
この点、スマートコントラクトについては、そこに記載されたコードそのものが契約になるのかという議論がありましたが、スマートコントラクトは契約それ自体ではなく、ブロックチェーン参加者間の契約を実現するツールであるとする考え方が有力という結果になりました。
ブロックチェーンについては、今後も論点化を見据えた検討を行うとのことです。
最先端法務の課題
今回、AIスピーカーやブロックチェーン技術についての法的性質について、記載されました。
事業者にとっては、技術はどんどん進化していきますが、法律面も検討する必要があります。最先端法務については、最新情報をチェックするようにしましょう。